���g�b�v�ɖ߂�
4��1���i���j���j�@�i�J�̂�����j
�@�@�@
���܂����������ʂ�Ɂ@
�ꂪ�u���ʑO�ɁA������i��x�j�ł悩����A�������Ő��܂�ĂӂƂ��i�傫���j�Ȃ����������i����j�ɍs���Ă݂����ˁ[�v�ƌ����̂ŁA�A��čs�����B
���s�吳��B
1945�i���a20�j�N�A12�̎��Ɍܓ��Ɉ����z�����̂�����A����70�N�ȏ㗈�Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B
�u�����[�A���c��͑S�R�Ȃ������B�ǂ����ǂ���������������S�R�킩����v
�܂��A�n�����Ȃ��Ȃ��Ă���B
���e������q�ɂȂ������ɂ����Ɍ�����悤�ɂƋ������܂�A83�ɂȂ��Ă����炷��ƌ������u�吳������ʂ�2����1�Ԓn�v�Ƃ����Z���E�n�Ԃ͍��͂Ȃ��B
�吳������ɍs���ĕ����Ă݂�ƁA���݂́u���1���ځv�����肪�̂̂��̒n�ɂ�����悤���Ƌ����Ă��ꂽ�B
��������ɍs���A������ӂ�����܂���Ă݂�B
�u���������i�S�R�j�킩���B�����ǂ�i�������j���Z��ǂ������́A��Ђ�Б����[���ƕ���ǂ����Ƃ�����Ăˁv
�u�吳���v�Ƃ����K���̑O�ɗ��āA��̖ڂ��ۂ��Ȃ����B
�u�����[�A���C�ɂᗈ�����Ƃ邲�Ă����B������͐V���イ�Ȃ������Ă�����āA�����������ܕ������ɘA��Ă��Ă��낤���̂͂��C����Ȃ��납���v
�u���C��O���A�����ǂZ��ǂ���������Ƃ��낽���v
�K���̑O�̒ʂ�̌��������A��̎w�����ꏊ������ƁA�����ɂ�10���K�����鋐��A�p�[�g�������Ă����B
�u������߂��̐�ׂ�̓L���E�`�N�g�E��������[���Ƒ����Ƃ��āA�Ԃ�т�����i��������j�炢�Ƃ��Ăˁ[�A�Ă͂���Ⴋ�ꂢ�Ȃ��������B����ǂ���ւ��������납���v
�u�߂��̏Z�g�_�Ђł̉čՂ�A�������E�ꂿ���ɘA��Ă����Ă���ĂˁA����i�K�j�����Ƃ��낤�āA���َq�����āi�����āj���炤�ꂵ��������B�ق�ƂŊy���������ˁ[�v
��������ɕ����܂���Ă݂����A�߂��ɂ���Ȑ�͂Ȃ����A�_�Ђ��Ȃ��B
��͈Ë��ɂ�����A�_�Ђ͓��������肵���̂��낤���B
������Ƒ��������ƐK����A�ؒÐ�A���ږx��ȂǂɂԂ���������ǁA�L���E�`�N�g�E�̕��ؓ����������ɂ��Ă͑傫������삾�Ƃ����C������B
����ɍ��̓R���N���[�g�̒�h����������ŁA�̂̂悷���͂Ȃ��B
�u�悩�悩�B�̂����͂Ȃ���i�����j�c���Ƃ�A����܂�킩���������āA���ʑO�ɂ����ɗ��������ł�߂��������B
�V���ւ̂悩�݂₰�̂ł�����B
���ꂵ���ˁ[�v
�A��Ă����b�オ�������ȂƐS����v�����ЂƎ��������B
�@�@�@���@�ȏ�̓G�[�v���[���t�[���łł��B
�@�@�@�@�@ ���ۂ́A
�@�@�@�@�@ �u�ꂿ���A�����܂ꂽ�w�����ʂ�x�ɍs���Ă݂�H�@�A��Ă������v�ƌ����Ă��A
�@�@�@�@�@ �u�悩�B�����v�̓łɂׂ��Ȃ��p�����ꂽ�B
�@�@�@�@�@����A���ɏZ�ޏf��i���̎o�j�W�̖@�����������܁A
�@�@�@�@�@��l�ŕ����Ă݂��B
�@�@�@�@�@�����ꏏ�ɖK�˂�ꂽ��A��̂悤�ȉ�b�ɂȂ����낤���B
���F �@ �u�����ʂ�v�Ƃ����n���͍��͂Ȃ��B



��̐��܂������n�@1�@���1���ڂ̌f���� �@�@�@ ��̐��܂������n�@2�@�@����̃A�[�P�[�h�X ��̐��܂������n�@3�@�@�@�e�q�ŕ�炵�������Ղɂ͍��͍��w�A�p�[�g��
���F �@ ���������I�ȕ��͋C���c���Ă���Ɗ������B
�E�F �@ �ꂩ�畷�����Ƃ���ł́A�����͏����Ȍ����̒���������ł��āA�Ƃ̑O�ɂ͏����Ȕ����������B
�@�@�@�@����͎Б�ŁA�c���i��̕��j�͂������̖a�эH��Ń{�C���[�W�Ƃ��ē����Ă����B
�@�@�@�@���͍��w�̎s�c�Z��ƂȂ��Ă��āA�u���̊��B
�@�@�@�S�F �@ �K���̂��������͔s�풼��̂��Ƃ����������Ă��āA�����̒����̂悤���Ȃǂ�����Ă��ꂽ�B



��̐��܂������ꏊ�@4�@�@�@�����̌������ɂ������Ƃ����K���͂����H ��̐��܂������ꏊ�@5�@�@�@�I�n ��̐��܂������ꏊ�@6�@�@�@�ؒÐ�B���̓L���E�`�N�g�E�炭�y��H
�@�@�@�@�ؒÐ�̃R���N���[�g��h�̐�ɂ́u���Z���h�[���v�������Ă��āA����̕ω����@���������B
�@�@�@
4��2���i�y�j���j�@�i����̂��܂�F�앗���߁j
�@�@�@
�u�@�X�e�[�L���������Ă��Ă���Ȃ̂��@�v�@�i�@�u�@�V�˃o�J�{���@�v�@�j
�����O�A���l�Ɖw�O�̋������ň��B
��̎v���o�������Ȃ�����ʂ̘b��ɂȂ�����A���ꂱ��Ƃ��킢�Ȃ��b�������B
�r���ŁA�u�V�˃o�J�{���v�����߂Ď��ʉ�����挎�i3���j�������ꂽ���Ƃ��A���̓��e�����Ă�������B
�h���}�̒��ŁA�����O�̃o�J�{���p�p�ƃ}�}�����ȃ��X�g�����ŐH���������ʂ��������Ƃ̂��ƁB
�X�e�[�L�̏Ă������ɂ��A���͂ł́u���A�v���́u�~�f�B�A���v�Ȃǂ̐����������钆�A
�o�J�{���p�p�����̂Ƃ���ɂ����X�g�����̕����Ă��������ɗ����B
�o�J�{���p�p�̕Ԏ���
�u�X�e�[�L���������Ă��Ă���Ȃ̂��v
���͂ł̓o�J�ɂ�����A�N�X�N�X���̉Q�B
����Ȓ��A���x�̓}�}���Ă����������B
�}�}�̓�����
�u�������������������v
���͂̏����̓n�^�Ǝ~�܂�A�V�[���ƂȂ����B
�ƁA�����܂ŕ��������A���܂炸�勃�����Ă��܂����B
�o�J�{���p�p�̕Ԏ��������A�Ȃɂ�犴�ɂ܂���̂�����A���Ɩڂ��E���E�����Ă����B
���Ƀ}�}�̂��Ƃ������ɂ͂��Ȃ���~�߂悤���Ȃ������B
�킽���́u�A�j�L�A�Ȃ�ŋ����́B����͋����悤�Șb����Ȃ����낤�v�Ƃ����B
�Ȃ��Ȃ̂������ł��킩�炸�B
�f�p�����̂��̂������ӔN�̕�̎p�Əd�Ȃ��Ă��܂����̂�������Ȃ��B
�����āA���̑f�p���ɏ_��ɁA�������B�R�Ɗ��Y�����Ƃ���}�}�̌��������Ƃ��́A�����_���A�̏�Ԃ������B
���F �@ 3��21���̎ʐ^�B



�ԍH�@�؉ԁH �@�@�@ �{���̐H��12�� ���r���O�X�g���f�[�W�[
�@�@�@�@�ʐ^�����͓E��ł�������A�E����1����䥂łĂ��Ђ����ɂ������́B
�@�@�@�@����3���́A���̂���������݁H�ɍ��ꂱ��ł��܂����B
���F �@ ���炭�Ƃ��邱�ƂɂȂ����̂ŁA���݂����Ȗ�Ȃǂ����H���ėⓀ�ۑ����邱�Ƃɂ����B
�@�@�@�@���ォ��V�C�^�P�A�V���W�A�ʃl�M�A�T�c�}�C���A�Ԉ����j���W���A�T�g�C���A�S�{�E�A�j���j�N�A�V���E�K�A���l�M�A�_�C�R���A�u����12��ށB
�@�@�@�@��������ׂĈꏏ�Ɏς��R�V���E�ʼn���������B
�@�@�@�@���ʂ������܂��A���������ėⓀ����B
�@�@�@�@����A�𓀂��A���X��G�߂̖�����Ďς��߂u�����̈���X�`�v�ɋ߂����̂ɂȂ�ƐM���Ă���̂����A�͂����āH
�E�F �@ �m�l��̂��́B
�@�@�@�@100�{�قǒ����ĐA�����䂪�Ƃ̂��̂͂܂�����ق�Ƃ����炢�Ă��Ȃ��B
�@�@�@�S�F �@ 3��21���̎ʐ^�B



���̓���@1�@�@�@�ڐ��H�O ���̓���@2�@�@�@�ڐ��H���� ���̓���@3�@�@�@���v��
�@�@�@�@���̓��̗[�����f�ڂ���̂�3��ڂ��B
�@�@�@�@���x���Ȃ����Ă����O���Ȃ��B
�@�@�@
4��3���i���j���j�@�i�J�F�Ԍ��͂ł������H�j
�@�@�@
�u�@�I�`���`���ق����B�����������Ă��ā@�v�@�i�@2�@�j
�m�l�̑���2�̏��̎q�B
���Ɛ�������3�ɂȂ�B
���܂ł͐e�̌������Ƃɂ͂��ׂď]���A
�u�ʐ^�B���A�͂����āv�ƌ��������ɖ��ʂ̏݁A�J�������ӎ�������ɂȂ��Ă���Ă����B
���A���̓J�����������Ă������ۂ���������A�������Ȃ��ӂ��������B
�����ȏ�ʂŁu���₾�v�Ƃ������Ƃ������Ȃ��Ă����B
�ȉ��͍ŋ߂̌����B
�A�p�[�g��10���K�A�x�����_�̓y�ڂ����|�����Ă����e�Ɍ������āB
�u���̓y�A�N�������Ă����낤�ˁB�J���X���|�[���Ǝ����Ă����i�����Ă����H�j�̂��ȁH�v
�p���c�𒅑ւ������Ă���Ă��镃�e�Ɍ������āB
�u���������A�c�����i�����j�ɂ̓I�`���`������H�v
�u�Ȃ���v
�u�c�N�ɂ��c�N�ɂ�����ˁB���������ɂ�����ˁB�ǂ����āc�����ɂ͂Ȃ��́H�v
�u�c�N�͒j�̎q������ˁB�c�����݂����Ȃ��ꂢ�Ȏq�ɂ͂Ȃ���v
�u�c�����A�I�`���`���ق����B�����������Ă��āv
���t���s���������������Ɠ����ɁA������u��ꎟ���R���v�̐^���Œ��ƂȂ��Ă���悤���B
�Ƃ͂����A����قǂ܂ő������Ă����̂ɕ����Ȃ��ӂ��������n�C�n�C�̏�Ԃŏ����܂������A�M���r���`���[�`���[�z���Â������̐Ԃ���t�ɂȂ�����A�u�Ԃ����Ԃ�v��ԂƂȂ邱�Ƃ�����B
�������O�ɖ������܂�A
������ɐe�̊S�����������Ƃ������������낤�B
�ނ��������N���낾�B
����A�q��Ă͂��ł��ނ����������X�̘A�����B
�����₩�Ȑ������F��B
�S�F �@ 3��21���̎ʐ^�B



�̉ԁ@1�@�@�@�R�}�c�i�̉� �@�@�@ �̉ԁ@2�@�@�@�L���x�c�̉� �̉ԁ@3�@�@�@�_�C�R���̉�
�@�@�@�@�A�u���i�Ȃ̉Ԃ̂��č̉ԂƂ����Ƃ̌������Ƃ�A�����݂͂ȁu�̉ԁv�B
�@�@�@�@�R�}�c�i�̉Ԃ͈�ʓI�ȍ̉Ԃɋ߂��B�L���x�c�̉Ԃ͐F�W�����b�p�̂悤�ȉԕفA�_�C�R���̉Ԃ͔��ȂǁA�悭�݂�̉Ԕ��̂��̂Ƃ͂����Ԃ�Ⴄ�B
�@�@�@�S�F �@ 3��17���̎ʐ^�B



�P���Ɖ���@ �J���R���I�Ƌ��D�̌Q��H �I�m�g�b���ƃ}���A��
�@�@�@�@��\���߂��O�����A���̓��͓�ʼn����B�Ă��v�킹�鏋���������B
�@�@�@�@���̌�͂܂�����ɖ߂�A�Ȃ��Ȃ��C�����オ��Ȃ����������Ă���悤���B
�@�@�@�@���̓��̓J���R���I��}���A���̌������ɂ͐�����Ȃ��قǂ̋��D���������Ă����B
�@�@�@
4��4���i���j���j�@�i�J�̂��܂�A�ߌ�x�����琰��F����17���������ɂ�15���B��߂Ȃ��V�C�̂悤���j
�@�@�@
�u�@�ł̊C�Ɂ@�v�@�i�@�u�i�r�B�̗��v�@�j
��N���ɕ��ǂƂ݂��S���Ȃ����ƒm�������A�Ȃ��������������̂������������������B
87�������Ƃ̂��ƂŁA����4�ΔN�ゾ�����ȂƍĊm�F�����B
15�N�قǑO�A�u����炳��v�ł̂������͉��₩�ȏΊ�A������肵�������ň�Ԃ̑��݊��������B
������3�l�̎q�ǂ������Z���E���w���łނ��������N����B
�������A���̘A���e���r��������������ɂ݂邱�Ƃ��ł����̂ŁA�e�q��Z�퓯�m�̉�b���L���ɂȂ����v���o������B
�u����炳��v���I����Ă��炭�̂��A�Ƒ��ʼn���ɍs���@�����A
�z�e���̃e���X�Łu�i�r�B�̗��v�̖�O��f��s��ꂽ�B
�Ƃ݂�����̉��ꖯ�w�~���[�W�J���H
10���N�O�̋L���Ȃ̂ł�������o�������A�Ƃ݂���̉��Z�́u����炳��v�̎��ȏ�ɉA�e�ɕx��ł���A�������������܂��ȗ��݂̂��䂫�����z�I�ɖ��킢�[�������Ă����B
���N�A��Y�����v�Ɖ���̗���ŕ�炷�����E�i�r�B�i�Ƃ݂���j�̂��ƂɁA�s��̐����ɔ�ꂽ�������v���Ԃ�ɋA���Ă���B
�ޏ��̏���Ă������D�ɂ́A�Ȃ��60�N�O�ɕʂꂽ�i�r�B�̗��l������Ă����B
60�N�O�A�Ȃ���l�͕ʂ�邱�ƂɂȂ����̂��H
���l�͉��̂��߂Ƀu���W������A���Ă����̂��H
�i�r�B�͒��N�A��Y�����v��I�Ԃ̂��A����Ƃ�60�N�O�̎v���𐋂���̂��H
����̖��w�╗�K������߂A�������m�푈���߂Â�����ɂ��e�𗎂Ƃ��Ă��Ă���悤�����`���A
�i�r�B�̕���͐i��ł����B
��l����鏬�M���ł̊C�ɐÂ��ɏ������ʂŕ���͏I������̂��������B
�������v��������l�����邯��ǁA����ł悩�����̂��A���ꂵ���Ȃ������̂��Ƃ̎v�����킢���B
�ق̂��ɓ�l����ł����ł̊C�̌��z�������ׂĂ�����Ă���銴���������B
�F������
�S�F �@ ����A�R�����b�B�s�ɍs���A��̂����̍��߂��B



���_���̍��@1�@�@�@�C�g�U�N�� �@�@�@ ���_���̍��@2�@�@�@�C�g�U�N�� ���_���̍��@3�@�@�@�C�g�U�N��
�@�@�@�@�̉Ԕ��Ɉ͂܂ꂽ���_���ɂ݂͂��ƂȂ�������i�C�g�U�N���j���������B
�@�@�@�@����300�N�قǂ̘V�ŁA5�C6�N�����Ė̍Đ��Ɏ��g��ł���Ƃ̂��ƁB
�@�@�@�S�F �@ ��O�͍̉Ԕ��B



���_���̍��@4�@�@�@��O�̍̉Ԕ� ���_���̍��@5�@�@�@�C�g�U�N���̊� ���_���̍��@6�@�@�@�剡�̃c�o�L
�@�@�@�@���̉��ł͒n���̂��������E������A�����Ă����A����̉��H�H�i���Ă����B
�@�@�@�@�݂Ȃ����������ŁA�E�h�A�^�N�A���A����̊����u�h�E�Ȃǂ����ꂱ��Ɣ����Ă��܂���
�@�@�@
4��5���i�Ηj���j�@�i�܂�B���サ�B�����Ɩ�����͉J�͗l�j
�@�@�@�S�F �@ �ԓ��ł������ł��A���������ŃT�N�����݂��Ƃ��B



����̍��@1�@�@�@�����u �@�@�@ ����̍��@2�@�@�@�_�� ����̍��@3�@�@�@�_��
�@�@�@�S�F �@ �J�Ԃ��Ă��犦�����������̂ŁA�Ȃ��Ȃ��U�炸���ꂵ�B



����̍��@4�@�@�@������ ����̍��@5�@�@�@������ ����̍��@6�@�@�@������
�@�@�@�@�E�̎ʐ^�̍��͖̍������A�قƂ�ǒn�ʂɍ炢�Ă���B���߂Č�����i�������B
�@�@�@
4��6���i���j���j�@�i�܂�̂��J�B��J���H�j
�@�@�@�S�F �@ 3���i���j�A�R�����b�B�s�̂����̍��B



���ю��̍��@1 �@�@�@ ���ю��̍��@2 ���ю��̍��@3�@�@�@�Ԃ̉��E��
�@�@�@�@���_���قǐl�͑����Ȃ��A�������ɂ�1�{�̃T�N��������̂݁B
�@�@�@�@���ꂪ�܂��悩�����B
�@�@�@�S�F �@ ���̂�������̒��ɓ���ƁA�Ԃ̒��ɂ��镗��B



���ю��̍��@4�@�@�@�Ԃ̉��E�� ���ю��̍��@5 ���ю��̍��@6
�@�@�@�@�n��������tࣖ����y����ł���悤�������B
�@�@�@
4��11���i���j���j�@����
�^�ē����Ǝv�킹�����Ƃ����ĕς���Ė{���͖k�������������A�ߌ�x���ɂ͔������Ȃ����B
����ł��䂪�Ƃ̋C���v�ł͍ō�22������������t�Ƃ��Ă͏����ق����B
�{���̍�Ɓ@�@ �@
�@�@�@�u���̔��v�ɃJ�{�`���i5�j��A�B�@�@�@�u�Ƃ̑O�̔��v�Ƀi�X�A�g�}�g��A�̏���
�@�@�@�S�F �@ 12�����߂ɐA���t���A�����}���`�ƃr�j�[���g���l���������Ĉ�Ă����́B



�W���K�C���@��@1�@�@�@�@��O �@�@�@ �W���K�C���@��@2�@�@�@�ꐤ�����@�� �W���K�C���@��@3�@�@�@�咆��
�@�@�@�@��N�͖��n�̕��t�y����ꂽ�������肪�o�Ă��h�����A���̂����ő��ɕ����Ă��܂��s���|���ʂ��炢�̂��̂����ʂ������Ȃ������B
�@�@�@�@���N�͔��ȓ_�����Ĉ�Ă��b�゠���āA�ʂ��傫���������߁B
�@�@�@�@���������Ă��ĐH�ׂĂ݂��B
�@�@�@�@�̂ꂽ�ĐV�W���K�͔炲�ƐH�ׂ��A�����B
�@���F �@ �_�C�R���̉Ԃ͏����̋��t�߂܂Ő������Ă��āA�|�����炢�̔ɂ�悤���B



�_�C�R���̉� �؉Ԃ̉� �Ί_�̃I�X�e�I�X�y���}��
�@�@�@�@�H�ׂ镔���̍��������̂ӂ���͂��قǂɋ��剻���Ă��Ă݂��Ƃ��B
���F �@ �؉Ԃ͉Ԃ��I���T�����ǂ�ǂ�Ƒ傫���Ȃ��Ă��Ă���B
�@�@�@�@�����V���H�p�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B
�E�F �@ �u�Ƃ̑O�̔��v�ƉƂƂ̋��ɂ���Ί_�ɁA���t�݂��Ƃɍ炭�B
�@�@�@�@��́u����Ԃ͂悤�f����i�悭�f����j�ˁ[�B���ꂩ�i�Y�킩�j�ˁ[�A�݂��ƂȂ���ˁv�Ƃ悭�Q�܂��Ă����B
�@�@�@
4��12���i�Ηj���j�@����̂��܂�
�{���́A5:35�ɖ��͂��߂��E�O�C�X�̐��Ŗڊo�߂��B
���̏o��5:55������A20�����O�ɖ��n�߂Ă���̂��ȂƋ����B
�ꂪ�S���Ȃ������X����2��26���͂��ʖ閾���̍��ʃ~�T�i���V�j�̓��B���̓����E�O�C�X�̐��Ŗڊo�߁A���v��������6:30�������B
���V�C��������Ƃ��̓��̓��̏o��6:57�B�閾����2�C30���O���炢������n�߂�̂����ۂ̂悤���B
���������������A����̖k���ɑ������͓앗�B
�_��Ƃ̓V���c1���ŏ\���������B�䂪�Ƃ̋C���v�ł͍ō��C��26.2���ŁA����Ȃɏ����������ȁH�Ǝ�����������B
�u�@�����[�A�������ق�ƂŐ��܂�ď��߂ĊC�ɓ�������[�@�v�@�u�@�����́[�A�킾��������Ȃ����Ȃ����@�v
�����ɋL���͖̂ʉf�䂢���A�{����35��ڂ̌����L�O���B
�u�I�V�h���v�w�v�ɂ͂قlj������A�܂����������ƂɈӖ�������̂��낤�Ɗ�����B
��̌���������30�N�Ԃ������B
19�Ō������A49�̎��ɕv�����E�B
���낢��Ƌ�J�������������A�S���Ȃ������͎q�ǂ�7�l�A��16�l�A�Б�7�l�����āA�܂��v���c�����ƂȂ������������Ǝv���B
�R�`�ɏZ�ދ`��͕��萔�ΔN���ŁA���������C�B
�`��ƕ��2�x����Ă���B
��x�ڂ͏�����̌������̎��B
������x��20�N�قǑO�A�ܓ���K�˂Ă��ꂽ�B
�����O�Ɏq�Ɠ������A�`��ƃJ�~������̂�҂����B
��́A����O����u�����[�A���������k�قȂ킩����B�b����ʂ��������납���H�v�ƐS�z���Ă����B
�`����J�~����Ɂu���̂悧�`�A����ܓ��̂�Ƙb����ʂ���������˂���ǁi�킩��Ȃ����j�A���܂˂́i�C�ɂ��Ȃ���j�B���߂ƈꏏ�ɍs�������A�܂��Łi�܂������j�S�z�Ȃ��������v�ƌ����Ă����낤���B
�������A�������S�����Ȃ��B���߂����m�Ȃ̂ŁA���ꂱ��Ɠ�l�Řb���e��ł����B
�^�Ă������̂ŋ߂��́u���l�v�܂ʼnj���ɍs�����Ƃɂ��A�ꂽ�����U�����B
�u��A�������Ȃ���ׂ��v�E�u�����A�������Ȃ�����v�i���₾�B�������Ȃ����j�Ȃǂƌ����̂ŁA�u���i���̂܂܂ŊC�ɓ���A����1�����i���������čs���Ē��ւ��Ă�����������v�Ɠ`���A�A��čs�����B
�ŏ��͑���������ƊC�ɓ������x���������A�q�⑷���j���͂��Ⴂ�ł���̂����Ă��邤���A���ɓ�l�Ƃ����܂ŊC�̒��ցB
���ɂ͓������ɉB�ꂽ��A�݂��ɐ���������������ƁA�܂��ɏ����ɖ߂������̂��Ƃ�60�ゾ�����B
�u�@�����[�A�C������悩�ˁ[�B�������ق�ƂŐ��܂�ď��߂ĊC�ɓ�������[�@�v�i��j�@
�u�@�����́[�i�����Ȃ�ł����j�A�킾��������Ȃ����Ȃ����@�v�i�`��j
�u�@�����A��l�Ƃ����܂�ď��߂Ă����Ė{���ł�H�@�т����肶��ˁ[�B����������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��낤�ŁA�悩���r�݂̂₰��ł��������@�v�i�����j
�Ƃ����悤�Ȃ���肪�������B
�����Đ����̂Ƃ���ɂ��ꂢ�ȊC������B
����ȏ���12���炸���ƏZ�ݑ����Ă��Ă��y���݂Ƃ��ĊC�ɓ���E�j���ȂǂƂ������Ƃ͈�x���Ȃ������ȂƎv���B
�Ȃ����������͓�l�̕ꂪ�C�̒��Ő������������Ă�������v���o�����B
�{���̍�Ɓ@�@ �@
�@�@�@�u���̔��v�ɃJ�{�`���i10�j�A�X�C�J�i10�j�A�������i10�j��A�B�@�@�@�u�Ƃ̑O�̔��v�Ƀi�X�i8�j��A�B
�@�@�@���F �@ �X�i�b�v�G���h�E�A������G���h�E�Ƃ��H�ׂ���Ȃ��قǂɐ������Ă����B



�G���h�E�̉� �@�@�@ �l�M�V�� ���r���O�X�g���f�[�W�[
���F �@ �l�M�V��͍����߂�����藎�Ƃ��đ��̏ꏊ�ɉ��A�����A�����������A����B��������܂����������l�M���H�ɐH�ׂ���Ƃ̂��ƁB
�E�F �@ ���ߏ���100���قǒ����������̔����B �z���Ƃ�Ƌ}�ɍ炭�B�݂��Ƃ��B
�@�S�F �@ 3��20���̎ʐ^�B



����@�ƃ}���}���� �J���R���I�ƊC�@1�@�@�@�k���� �J���R���I�ƊC�@2�@�@�@�����
�@�@�@�@�����͊C�ɍs�����B�@�ߑO�̐���Ԃ̎��͂���Ȋ����������낤�B
�@�@�@
4��13���i���j���j�@�܂�̂��J
���̗\��ł͒����������J�Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA�{���͏����d���݂̂Ɗo�債�Ă����B
���A�����ɖڊo�ߊO������Ƃ܂��~���Ă��Ȃ��B
����ĂĒ��H�����������ɍ̉Ԑ������A�g�}�g���A�����B
�r���J���~���Ă������A�Ȃ�Ƃ���A���I�������ɂ͂�݁A���邭�Ȃ�B
���H���I���Ă��܂����邢�̂ŁA������d���ł��邩�Ɣ��f���A�L���E����������A�����B
�A���I��肪�߂��ߌ�3�����납��y���~��ɁB �܂��J���ŕc���܂�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̊�����x����s���ۉ�������d�����c���Ă���̂ŁA���H�𒅂č�Ƃ𑱂���B
���H��ʂ��ĉJ�����ݍ���ł��ĉ����܂ł��ԔG��ɂȂ�B
���ǁA�ʏ�̓�������1���ԑ������炢�܂ŊO��Ƃ������B
�J�ɐU��ꂽ����������B
�{���̍�Ɓ@�@ �@
�@�@�@�u�Ƃ̑O�̔��v�Ƀg�}�g�i16�j�A�L���E��(16)��A�B
�@�@�@�S�F �@ ��������A�@�́A1�����قǑO�ɐ��𗧂ĂĔ엿���{���Ă����A�엿���y�ɂȂ�����ɒ�A����B



�؉Ԑ����i�X���Ɂ@1�@�@�@�������O �@�@�@ �؉Ԑ����i�X���Ɂ@2�@�@�@�������r�� �؉Ԑ����i�X���Ɂ@3�@�@�@�i�X��A��
�@�@�@�@�����̓s����1���Ő��Â�������A��A���Ă��܂����B
�@�@�@�@�s�k�N�͔|�̂������A����Ȃ���y�A���ł��܂��܂��̎��n���ł��Ă���B
�@�S�F �@ �ߌ�A�y���~�肪�����ԑ������̂����~��ƂȂ�A�[��ꎞ�͏��������[�Ă���ƂȂ����B



�J�A�ߌ�̊C �J�オ��A�[���̊C �J�オ��A�[���̃}���A��
�@�@�@�@�����Ƃ肵�Ă�������B
�@�@�@
4��14���i�ؗj���j�@����
���x�������A�k�����������̐���̓��B
����ł��킪�Ƃ̋C���v�ł͍ō��C��26.2���B
�f�W�^�����x�v�ŁA���ɒu���Ă��鐅��C���v����2���قǍ����X��������̂����A����ɂ��Ă�����Ȃɏ��������̂��Ǝv���B
��ƃT�C�N�����O�H
�u��Ƃ�������ɃT�C�N�����O�����Ă���B
�T�N�������J�ŁA�̉Ԃ��炫����Ă���Ȃ��A�y�������ȏΊ炾�B
����ł�������ɏZ��ł��āA������Ƒ̒��������Ƃ����̂ŕa�@�ɘA��Ă����Ă̋A�蓹�B
��҂���u������Ɣ]���������̉\��������܂��ˁv�ƌ���ꂽ�B
�������ɑO�𑖂��̃n���h�������͂��ڂ����A�ǂ����ӂ���Ă���悤���B
������͎d��������̂Ŏl�Z������̂��ɂ��ĉ�삷��͖̂��������A�ƔY��ł���B
�ܓ��ł�������ɕ�点�A���d�������Ȃ��������ł邱�Ƃ��ł��邩���ȁA�Ȃǂƍl���Ă���B
�ƁA�����ŁA�Ȃς��ȂƎv���B
���60�Α�㔼�܂Ńo�C�N�͏��Ă������A���]�Ԃɂ͏��Ȃ������͂��B
����Ɋ��ɉ��N���ܓ��ł�������ɕ�炵����Ȃ��������B
����ɕ�͂����c�c
����ȕ��Ɏv���n�߂������ɁA�w��������A�ς���x�Ƒ��Â���ł�����l�̎���������B�v
�@�@�@�ƁA�����œ�l�̎����Ƃ������āA
�@�@�@�z�c�̒��ɂ���A�����킷�E�O�C�X�̐��Ŗڊo�߂�����������B
�@�@�@�������Ă���ƁA������2�l��3�l������Ƃ����ɂȂ�̂��H
�@�@�@�����̖��͂��ɂ������ă��A���������B
�{���̍�Ɓ@�@ �@
�@�@�@�u���̔��v�̐Ί_�ɃI�X�e�I�X�y���}���̒�A�B�u�Ƃ̑O�̔��v�Ԓd�̑����B
�@�@�@���F �@ 4��1���Ɍf�ڂ����u���s�吳�����v�̎ʐ^�́A2�N�قǑO�A�f���̂�����݂ɍs�����Ƃ��̂��́B



��̐��܂������ꏊ�@1�@�@�@���͋���A�p�[�g�Q�� �@�@�@ ��̐��܂������ꏊ�@2�@�@������X�X ��̐��܂������ꏊ�@3�@�@�@������Z
�@�@�@�@��T�A���삩��ܓ��ւ̋A��A�������d�ԂŐ����Ԃ̂Ƃ���ɏZ�ޖ���l�ƍĂіK��Ă݂��B
�@�@�@�@�ꂽ�����Z��ł��������Ղɂ͍��w�A�p�[�g��9���������Ă����B
�@�@�@�@�c��(��̕�)�͖a�эH��̃{�C���[�}���������Ƃ̂��Ƃ����A���Ԃ�H�ꉡ�ɕ��݂��ꂽ�����������̂��낤�B
���F �@ ������X�X�͂܂��l�ʂ���������ꂵ���B
�@�@�@�@�������A�߂��ɃC�I�����ł��Ă���͏��X�ɋq�������Ă��Ă���Ƃ̂��ƂŁA����͂��������������ȂƎv�����B
�E�F �@ �u���w���߂łƂ��v�̐��ꖋ���܂Ԃ����B
�@�@�@�@�u�ܓ��Ɉ����z�����Ȃ�������A�ꂿ���͂��̍��Z�ɓ����������ȁv�ƌ����ƁA
�@�@�@�@���Ɂu�Z�����A���a30�N���됶�܂�̎����������Z�ɂ͍s��������₩��A���a7�N���܂�̕ꂿ��s�����킯�Ȃ����B���̂��덂�Z�ɍs���Ƃ�����́A���̑�w�ɍs�������������Ƃ������H�v�ƌ���ꂽ�B
�@�@�@�@�܂��ɂ��̂Ƃ���B
�@���F �@ ����͐K����ɖʂ��Ă���A�Ί݂͍`��s���B



��̐��܂������ꏊ�@4�@�@�@�K���� ��̐��܂������ꏊ�@5�@�@�@�s���B�����Z�A�p�[�g�� ��̐��܂������ꏊ�@6�@�@�@�������
�@�@�@�@�ʐ^�̍���������ŁA�E�����s���B
�@�@�@�@����l��35�N�قǑO�Ɏs���ɏZ��ł����B
�@�@�@�@�������Z��ł����A�p�[�g�Ղ܂ŋ���n���ĕ�������A30����Œ������B
�@�@�@�@�܂��������������Z��ł����ꏊ����2�C30���������Ƃ���ɕꂪ���܂������n���������Ƃ́B���߂Ēm���āA�����������肾�����B
�@�@�@�@���R�Ƃ͂����A�����[���B
���F �@ ���������Z��ł����A�p�[�g�͂�����u�����Z��v�B
�@�@�@�@�Â����ŁA�Â��L���ɋ����������Y���b�ƕ��сA�j���������ĕ�炵�Ă���̂Ƀg�C���͈�����Ȃ������B
�@�@�@�@�g�C���ɍs�������Ȃ�����N�������Ă��Ȃ����A�����Ă����炢�o�邩���܂��Ă���˂Ȃ炸��ς������Ƃ͖��̒k�B
�E�F �@ ��������̓T�N�������J�B
�@�@�@�@�n���̂��������e�q�A�ꂪ�ٓ��������ĉԌ������Ă����B
�@ �@�@�@
4��15���i���j���j�@����
���̖�10������A����ɏZ�ގq������d�b����B
��قnjF�{�Œn�k�������ςȂ悤�������A�ܓ��͑��v���ƁB
��ւ̍��T�Ȃǂ��S�����������ɂ����������Ă����̂����A�h��͊������A�܂������m��Ȃ������B
�e���r�͂��Ă��炸�A�g�̉��������ɕ������邭�炢�̐Â����������̂����A������܂ł͉e���͂Ȃ������l�q�B
�����e���r������B
�v��������ςȏŖڂ��݂͂�B
��Ȃ̂Ŏ��͂̏������炸��ς��낤���A�債����Q���Ȃ������}���Ăق����Ɗ�����B
�{���̍�Ɓ@�@ �@
�@�@�@�u���̔��v�ɃX�C�J(8)�A������(6)��A�B�@�u���̔��v�̉Ԓd�̑����A�O���W�I���X�A���B
�@�@�@���E���F �@ ���p���������_�m�ȂցB



�t�@1�@�@�@�n�[�ƃA�P�r �@�@�@ �t�@2�@�@�@�H �t�@3�@�@�@�A�I�_�C�V���E�H
�@�@�@�@�r���A��t���݂��Ƃ������B
�E�F �@ 1.2m���₻��ȏ゠��݂��Ƃȃw�r�������B
�@�@�@�@���}�J�K�V�A�W���O���Ƃ͐F���Ⴄ�悤�����A�}���V�����X�}�[�g�����A��͂�A�I�_�C�V���E���Ǝv���B
�@�@�@�@�Ԃ�瀂��ꂽ�炵�����H�̐^�Ŏ���ł����B
�@�@�@�@�R�̒��ɕԂ��A�����Ă������B
�@�S�F �@ �C�����̂悢���B�v���Ԃ�ɒ��̊C������Ă݂��B



���̊C�@1�@�@�@�J���R���I ���̊C�@2�@�@�@�}���A�� ���̊C�@3�@�@�@�J���R���I�Ƌ��D
�@�@�@�@��u�Ԃ̑D�����Ƃ��Ă���A�ق��ɂ��ނ�D�����z���������B
4��16���i�y�j���j�@����̂��J
�钆��1������A�ً}�n�k����n�߁A���悢�悱�������n�k���Ɛg�\����B
�����̗h��ŏI��������A���̃j���[�X������ƌF�{�ł͂���ɔ�Q���L�������悤�����f���o����Ă����B
�����ł��Ȃ����A����܂Ŋւ�肪�������@�ւ�ʂ��Ă����������t���𑗂�B
��������ꂽ�����łȂ�������d�C�Ȃǂ̃��C�t���C�������f����Ă���悤�ŁA�����ɂ͒������Ԃ������肻�����B
������킹�A�����������F��B
������J�Ƃ̗\�����̂ŁA�ߌォ��͉����d���ɂȂ邾�낤�Ɠ��ݑ�������_��Ƃɂ������ށB
���A�[���܂ō~�炸�A����������Â��߂ł���ǂ������B
�Ƃ��낪���v�ƂȂ��Ƃ��I���悤�Ƃ����Ƃ���Ŗ\���J�ƂȂ�A�\���}�����|�ꂻ�����B
�������Ȃ����H�𒅂ĉ��̎x����⋭���A�����̈���������B
�{���̍�Ɓ@�@ �@
�@�@�@�u���̔��v�̃l�M�A���ւ��B�T�g�C���x��ƐA�t���B�@�u���̔��v�Ɓu�Ƃ̑O�̔��v�ɐ���̉Ԃ̎�d���A�T�t�B�j�A�A���t�M�N�̐A�t��
�@�@�@���F �@ �p���W�[�͂��킢�������ȂƎӂ�A���Α�����30���łł���̂����Ǝv���A�܂��ł����ɂ���B



���ɖ����ꂽ�p���W�[�ƃL�N �@�@�@ �A���ւ��O�̃l�M �l�M�����Ɖ𓀗���
�@�@�@�@�ꌎ�قǑO�ɂ��ꂢ�ɑ���肵���̂����A�܂������ɐ����ĕ����Ă��܂����B���������̂��B
���F �@ 40�{�قǂ��邤���A30�{��10�p�قǎc���Đ���A�ڐA�����B
�@�@�@�@6�����ɂ͕�������̂ł�����Ē�A����ƏH�ɂ͂��������l�M���H�ׂ���Ƃ̂��ƁB
�@�@�@�@���Ƃ�10�{�̓l�M�V����c���ĈڐA�����B
�@�@�@�@����͎���̂��āA�H�ɔd���Ă݂�B
�E�F �@ �ʐ^�E�͐������l�M���L�m�R�Ɠؓ��ƂƂ����u�߂����́B
�@�@�@�@���͐������O�ɂ������ρH�����Ⓚ���Ă������̂�߂������́B
�@�@�@�@�l�M�A�L���x�c�A�n�N�T�C�A�_�C�R���A�j���W���A�S�{�E�A�T�g�C���B����ɗg�������A�ؓ��A�u�������������A�j���j�N�ƃV���E�K������Ďύ��݁A���Əݖ��Ŗ��t�������B
�@�@�@�@����͂������������������Â�����A�܂���؏���Ɖh�{�⋋�̂�������i�ɂ͂Ȃ��Ă��邩�ȂƎv���B
�@�S�F �@ ����̎ʐ^�B



���ǃ��l �P���Ɖ���@ �I�m�g�b���Ɛ�����
�@�@�@�@���ǃ��l�͖����Ő���ł����B
�@�@�@�@�P�����ɂ��Ă��Č������B
�@�@�@
4��17���i���j���j�@����
���͗[������\���J�B����܂Ŗ���������Ƃ��Ȃ��قǂ̋����������B
�C�ے��̃f�[�^�ł͖钆�O��͕���13���B���ϕ��������ꂭ�炢�ɂȂ�ƍő�u�ԕ�����3�C40���قǂɂ��Ȃ邱�Ƃ�����A���̎��͗����Ă���͖̂����B���܂����Ⴊ�܂Ȃ��Ɠ|��ē���łB
���i�͕���7���ł��|�����炢�̕����Ɗ�����̂ɁA���̐����́I
���܂܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ��\���Ɗ������̂͐����������悤���B
�\���}���͍��̉��x���ݒu�œ|���͖h�~�ł�������ǂ��A����3�����炢���܂�Ă��܂����B���n�͌����ƂȂ肻���Ŏc�O�B
�����͑䕗��߂̗l���ŋC�����̂悢������a�B
�_�������͂���A�������邱�Ƃ��Ȃ��t���a�������B
�{���̍�Ɓ@�@ �@
�@�@�@�u���~���v�̈�c�p�g���l���Â���B�u�Ƃ̑O�̔��v�̉Ԓd�̑����B
����������
��X�T�A���삩��ܓ��ւ̋A��A���Ɋ���Ė���l�ƕ�̐��܂������ꏊ��K�˂��B
���̎��̕����Ȃ���̘b�ŁA�ܓ��̂킪�Ƃɐ����������ꂽ�̂͂������b��ɂȂ����B
3�Ή��̖��́u���w�Z�ɍs���Ƃ������@��Ԃ���Ă��̂͂��ڂ��Ă�B���ǁA��˂��琅������ŕ��C�ɓ��ꂽ���ڂ����͂���ւ�Łv�ƌ����B
���ǁA���������w4�N�A�������w1�N��1962�i���a37�j�N�ł͂Ȃ��������Ƃ������Ƃŗ����������B
����������O�A���w�Z2�N���납���2�C3�N�ԁA��˂��琅������ŕ��C�ɓ��������𖽂���ꂽ�B
��ׂ���˂ɓ������Ƃ��Ĉ�������グ�A3�t�قǂ��o�P�c�ɒ��߁A����C���܂�10���قlj^�ԁB
�����͓S���̌܉E�q�啗�C�ŁA���̗�����菬���������Ǝv�����A����ł�20�������炢���˂Ȃ�Ȃ������B
�����Č��ŁA�������|����̂��x���Ȃ�����A���n�߂Ă��_���_���Ƃ��̂ł͂��ǂ�Ȃ��B
���̏�A�������I������犘�̉��ɉ����A�d��R�₵�ĕ�������Ƃ�����B
��ǎd������A���Ă������ꂩ��A�u�܂������Ƃ��Ƃ��I�v�Ɠ{���邱�Ƃ������������B
����������A���ꂪ���������˂̐����^�Ȃ��Ă��悭�Ȃ�A�Ƃ����̂͘N�����B
�������A������̂���n�悩��킪���܂ł͂����Ԃ�Ɨ���Ă���A�����ǂ����݂���Ă���܂łɂ͂����Ԃ�Ǝ��Ԃ����������B
����Ƌ߂��܂ł��čH�����n�܂�ƁA�ʊw����ς������B
���w�Z�ɂ͖�3�q������Ă����̂����A���̓��̒����ɕ�1.5���A�[��2���قǂ̍a�������Ƒ����Ă���l�͈����������B
���̍a�̗��e�Ɍ@�����y�������Ă���A�f�R�{�R�̐���y�̏������Ēʊw���邵���Ȃ��̂Ŋ�Ȃ��������B
�����͏W�c�o�Z�ŁA�㋉���̖��߂��܂����w�����Ẳ������̈��S�ɋC��z��˂Ȃ炸�A�q���q���̓o�Z�H�������B
�����āA���ɐ����������B
���̊y�`�����͌��t�ɂ���B
���܁A�������Ȃ������m���Ă���l�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��邾�낤���A����Ȏ���ɖ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B
�������A�����v���o���B
�@�@�@�@���܌F�{�n�k�ł͐������~�܂��Ă���Ƃ̂��ƁB
�@�@�@�@�����Ȃ���ΐl�͐����Ă����Ȃ��B
�@�@�@�@�[���ȋ����⑁�}�̐����������肤�B
���F �@ 3��18���̎ʐ^�B



���t�̍̉Ԕ� �@�@�@ ���t�̓c��� �����̓c���
�@�@�@�@�̉Ԃ��`���z���ƌ����鑐��(�q��H�j�͒�����ɂ܂�Ă��Č��z�I�������B
���F �@ ������3��18���̎ʐ^�B
�@�@�@�@��N�H�̈���n���x�k�����݂̂ŁA���ɂ������Ă����B
�E�F �@ �����̎ʐ^�B
�@�@�@�@���̎ʐ^�̓c��ڂɂ͂��������͂��Ă���B
�@�@�@�@�߂��̓c��ڂł́A�������c���A�����Ă����B
�@�S�F �@ ���傤�ǂP�����O�A3��17���̎ʐ^�B�{���͊C�ӕ����ɍs���Ȃ��������A�����Ƃ���Ȍ��i�������낤�B



�A�I���ƃJ���R���I �A�I���Ɖ���@ �A�I���Ɖ���@�E�P��
�@�@�@�@�A�I���Ƃ͕����ŁA�C�̒��ɍ����͐ς��Ă��镔���̌Ăі��B
�@�@�@�@���������ƂȂ邨�����ŊC�̐F�ɂ����ω��������炵�Ă���B
�@�@�@
4��18���i���j���j�@�܂�̂�����
�قƂ�Ǔ܂��1���������B
��6������̒n�\����11���B���ꂪ1�����O��3��18����14���A3��22����5���������i�C���͏���15�C16�C11���j�B
�t�Ƃ͂����A�܂��܂����������͍s���߂���Ă���ȂƎv���B
�{���̍�Ɓ@�@ �@
�@�@�@�|�b�g�Ɏ�d���F�n�o�l���i6�j�A�s�[�}���i12�j�A�g�E�����R�V�i144�j�A�I�N���i6�j�A�S�[���[�i18�j�A�Y�b�L�[�j�i8�j�A�Ђ傤����J�{�`���i6�j�A�o�W���i6�j�A�~�c�o�E�V�\�E�V�����M�N�i�e32�j�B���������ǂꂾ���肪�o�邩�y���݂��B
�X�C�[�g�s�[�̎x�����āB�T�t�B�j�A�̂�����
�d�b������
����̑����B
����l�Ƙb���Ă��āA�ܓ��̂킪�Ƃɓd�b�������̂͂������b��ɂȂ����B
������19��1973�i���a48�j�N�ɂ͂܂��Ȃ������B
����2������G�ݓX�̂����̈�ɑ��B��̓d�b������A���̐l�S���A�d�b������K�v������Ƃ��͂����ɍs���Ă������B
�ߋ����̏ꍇ��10�~���Ă����Ƃ܂���B
�s�O�ǔԂɂ������ꍇ�́A�b���I������シ���ɎG�ݓX�̎�l���d�d���Ђɓd�b���i105���������j�A���̒ʘb�������B���̋��z���x�����Ƃ����V�X�e���������B
�t�ɓd�b���������Ă����ꍇ�́A�����ɕ�������g����Łu�c����A�d�b�ł��v�ƕ���������B
���������炻�̎G�݉��܂ő���B
100m����ȏ�̋����Ȃ̂ő�ς������B
���̈�Ԃ͂���̉Ƃ����3�A400m��������������Ƒ�ς������낤�B
���傤�ǂ��̎���4�N�Ԃ̋��D���������I���ē����̓d�q���w�Z�ɓ��w���鏀���̎����������B
�����ʐM�m�̎��i���擾���Ă���A���̊W�̎G���ɍڂ��Ă����w�Z�ɘA�������B
�����ł����w�A��ւ̖����Z�m���Ǝ����ɍ��i�ł�����Ɠ��e���Ƃ����B
���������w�����������Ζ������œ��w�ł��A���̂��������ꏊ�◾���Љ�Ă����Ƃ����B
���v�����܂�����b�ŁA���ǂ͂����ɑފw����H�ڂɂȂ�A�������w���Ǝ��Ɨ��̕������������B
�Ƃ�����A���w���̑��̎葱����Љ�Ă��������Ђւ̓��Ђ�����ɂ��Ă����Ԃ�Ɠd�b�̂��������A����̓d�b�����͍��z�ɏオ�����B
3�Ή��A5�Ή��̖��͒��w���ƌ�͊��̍H��ɏA�E�����̂����A�ޏ�����Ƃ��o��O�ɓd�b���������L���͂Ȃ��Ƃ����B
���ǁA�ޏ��炪�ܓ����o�������1975�i���a50�j�N������ɉƂɓd�b�������낤�ȂƂ������ƂɂȂ����B
���̎����G�s�\�[�h������A
�킪�Ƃ͉ƌv���ꂵ�������̂ŁA����́u�d�b�Ȃ�Ă��邱�Ƃ��Ȃ����A���邱�Ƃ��Ȃ�����A����Ƃɂ͈�����ł悩�v�Ɛ\���o���炵���B
�������A�d�b��ЁH����u������X�œd�b�����������Ǝv�������A������ɍH��������ƍ��z�̎x�������K�v�ɂȂ�B���S�̂ɍH�������Ă��鍡�̕����f�R�����ł���v�ƌ����A���Ԃ��ԏ��m�����Ƃ̂��ƁB
�J�ʂ�����A��������œ����q�ǂ��炩��Ƃœd�b���A�b�����Ƃ��ł����̂�����A��͂�v�����čH�������Ă�����Ă悩�����Ǝv�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�@�@�@���܌F�{�ł͌Œ�d�b���ʂ����ʐM�Ԃ����f����Ă���Ƃ̂��ƁB
�@�@�@�@�g�ѓd�b�ő�ւł��镔�������邾�낤���A����������Ȃ��ʐM��҂Ȃǂ͑�ς��낤�B
�@�@�@�@�����l�A�����������F��B
���E���F �@ ��N�̓G���h�E���������ӏ������L���E��16�{��A�����B



�L���E�����@1�@�@�@���Â���O �@�@�@ �L���E�����@2�@�@�@�c��A��A�A���h���ۉ� �̉�3��i�؉ԁA�ԃ_�C�R���A���j
�@�@�@�@���炭�̓A���h���ۉ��Ɠ|���h�~�����˂�B
�@�@�@�@���߂Ɏx���𗧂ăl�b�g�肽�����̂������ɂȂ邩�H
�E�F �@ �؉Ԃ͊��S�ɏI���A������ɂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�ԃ_�C�R���͐��F�B
�@�@�@�@���̉Ԃ͍炫�͂��߂�����A�l�̔w���荂���Ȃ��Ă���B
�@�@�@�@�����A�u���i�Ȃł������Ԃ�ƈႤ���Ƃ��B
�@�S�F �@ 3��9���̎ʐ^�B



�P���ƍr�C�@1 �P���ƍr�C�@2 �r�C
�@�@�@�@�����̖\���J�̎��͂���ȕ��������낤���B
�@�@�@�@���₱�̐��{�̍r����������̂ł͂Ǝv���B
4��19���i�Ηj���j�@����
�݂��ƂɈ�����_�Ȃ��̐�����a�B
�E�O�C�X��5:25�ɖ��n�߂��B
5:45�����̏o������s�b�^��20���O�ŁA�ł������A�d�g���v�ł������Ă���̂��Ɗ�����قǂ��B
�͓܂�̂�����������ƒx���5:33�������B
�u�߂����̊w�Z�v�Ȃ�ʁu�E�O�C�X�̊w�Z�v������Ȃ�A�搶�́u�݂Ȃ���A����͐Q�V�Œx��܂������A�����͐��������Ԃɖ��n�߂��܂����ˁB���炢�ł��ˁv�Ƃق߂Ă��邱�Ƃ��낤�B
����A�E�O�C�X�̖������͎q�����c�����߂ɑ���ɃA�s�[��������̉̂Ȃ̂�����A�������k�ł͂Ȃ����H
�{���̍�Ɓ@�@ �@ �u���̔��v�̃X�C�J�A�������ɐ����A�����~���B�u���̔��v�Ƀc�N�l��A���i16�j
�{�����e�B�A�̎d�����Ȃ��Ƃ����̂͊��������
�j���[�X�ŁA�F�{�n�k�ɂ��A�u���̓{�����e�B�A�ŗ�����͎̂��l���v�Ƃ̃A�s�[�����������B
�]�k�������Ă��邽�߁A���S���ۏ�ł��Ȃ�����Ƃ̂��ƁB
�����m�邽�߁u�F�{���Љ�����c��v�̃z�[���y�[�W�̃{�����e�B�A�����J���Ă݂��B
�������̢10�̐S���܂�����f�ڂ���Ă���A�u��Вn�ł̊����́A���n�̍ЊQ�{�����e�B�A�Z���^�[�̎w���ɏ]���čs�����Ă��������v�ȂǑ����̒��ӎ������������B
���̒��ɁA�u �ЊQ�{�����e�B�A�Z���^�[�ɍs���Ă���Ƃ��Ȃ��ꍇ������܂��B��Ƃ��Ȃ�����Ƃ����ē{��Ȃ��ł��������B����́A��������̃{�����e�B�A���Q�����Ă��邩��ŁA��������Ƃł�����܂��B�w�҂��Ƃ��{�����e�B�A�x�Ȃ̂ł��v�Ƃ������ڂ��������B
���̒ʂ�ŁA�u���������{�����e�B�A�ɗ����̂����牽���d�����������v�Ɨv������A�{�����e�B�A�̎d����T�����߂Ɍ��n�̃X�^�b�t���삯������Ƃ����̂͂܂������Ǝv���B
2007�N�́u�\�o�����n�k�v�̂Ƃ��A�֓��t�߂Ń{�����e�B�A�ɎQ���������Ƃ�����B
4���قǔN�x�����A���̂����������ł���H����e���g�E�Q�܂������ă{�����e�B�A��]�҂̏W���ꏊ�Ɏw�肳�ꂽ����w�ɍs�����B
��������X�^�b�t�̎w���ɏ]���A�o�X����ɕ��悵�Ĕ�Вn���������B
���������̂͗֓��̓���20�q�قǂ̑]�X�ł��������A������3�A4�l�̃`�[���ƂȂ��ďW�����܂����ۊm�F��������A�����Ă��邱�Ƃ₵�Ăق�����Ƃ͂Ȃ��������ĉ�����B
�K�^�Ȃ��Ƃɂ��̏W���͔�Q�����Ȃ��A��Ƃ͐����Ԃōς݁A�ߑO���ŏI������B
�������̔�Вn�Ɍ������̂��낤�Ǝv���Ă�����A�ҋ@���Ă��Ă���ƌ���ꂽ�B
�ڂ̑O�̍��l�C�݂Œ��H��������B
�ƂȂ�ɍ��������́u���ꂩ��삯���Ă����B��N�ɂȂ��Ď��R�̐g�ɂȂ����̂ł������͐l�̖��ɗ����Ƃ��������āv�ƌ���Ă����B
�ǂ����e�ӏ��Ől��͑���Ă���A���̃O���[�v��K�v�Ƃ��錻��͂Ȃ��炵���B
�X�^�b�t�͂���Ȍ����T���ׂ��d�b������Ԃő��������ςȂ悤���������B
���т�H�I����Ă���ƌ���͌�����Ȃ��悤�ŁA�ҋ@���Ԃ����������B
�{�����e�B�A�����o�[�̒�����u�҂��Ă��鎞�Ԃɉ������Ȃ��̂͂��������Ȃ�����A���̊C�݂�|�����悤�v�Ƃ̐����o���B
�S���Ő����Ԃ����ăS�~�◬���E���W�߁A���������ȏd�J���������B
���ǁA���̓��͐V���ȍ�Ƃ͂Ȃ��A�邱�ƂɂȂ�A�o�X�͗֓��s�̔�Ќ����ʂ�A�X�^�b�t���n�k�����̗l�q�̐��������Ă��ꂽ�肵���B
���ׂ���Ƃ��Ȃ��Ƃ����͔̂�Ђ����Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�u��������Ɓv�������̂��Ƃ��܂���Ɏv���B
�@�@�@�@����Ȃ��Ƃ��v���Ă��邤���A��ɂȂ��ăj���[�X������Ɓu�F�{�����{�����e�B�A���W�J�n�v�Ƃ̂��ƁB
�@�@�@�@�������͍s���Ȃ����A���Ԃ���ꂽ��l�������Ǝv���B
�S�F �@ ��X�T�A���삩��ܓ��ւ̋A��A��ܓ��œ�����ɉ���ē������w���A�����D������̐�y��ɔ��߂Ă����������B



��ܓ��@1�@�@�@�������V�哰 �@�@�@ ��ܓ��@2�@�@�@�������V�哰 ��ܓ��@3�@�@�@�ᏼ�t�߂̃A�U�~
�@�@�@�@���D������̏o�`�O�̖�A�ޗǔ��̂��̐�y��ɂė[�H�����Ƃ���������A�������ӂł���B
�@�@�@�@���������45�N�ȏ�O�ɂȂ�̂��Ɗ��S�[���B
�@�@�@�@�ܓ���140�]��̓�����Ȃ邻�������A��v�T���̂����k�̒��ʓ��Ǝᏼ������ܓ��i�ޗ����A�v��A���]�������ܓ��ŁA��������炵�Ă���͕̂��]���j�ƌĂ��B
�@�@�@�@��Ƃ͐��E��Y���̍\���{�݂ɂ��Ȃ��Ă��铪�����V�哰�Ȃǂ̋���A���]�̂悢�ꏊ�Ȃǂ��������B
�S�F �@ ���ܓ��Ƃ͂܂��Ⴄ���͓I�ȓ���]�⒭�߂�����A�Â������������B



��ܓ��@4�@�@�@�L���̊C ��ܓ��@5�@�@�@�˂̗[�� ��ܓ��@6�@�@�@�y��̉Y
4��20���i���j���j�@����̂��܂�
���߂��܂ł͉����B�_�͂܂������Ȃ��A�ō��C���͂킪�Ƃ̋C���v�ł�28.7���܂ŏオ�����B
�C�ɎU��ɍs�����c�O�B
�������ߌ�x������}�ɓ܂��Ă��āA�[���ɂ͉J���ۂۂƁB��x���ɂ͖\���J�ƂȂ����B
�g�}�g�ƃi�X�͊�����x���������݂̂ōs���͂����Ă��炸�B���Ő܂�Ȃ����S�z���B
�{���̍�Ɓ@�@
�u�O�̔��v�Ƀg�}�g�i4�j�A�S�[���[�i4�j�A�w�`�}�i2�j�A�I�N���i6�j��A�B�����ւ̃R���p�j�I���v�����c�Ƃ��ăc������G���h�E�i8�j�A���b�J�Z�C�i4�j�̎�d���B
�u�Ƃ̑O�̔��v�̉Ԓd�Ƀe�b�Z���A���x���_�[�A�o�W���A�f�[�W�[��A�B
����ł��C�w���s�̃L�����Z��������
����A�_��Ƃ����Ă��鎞�A���ɏZ�ޒm�l���ԂŒʂ肩����A������Ƃ��������b�������B
�����E�����ƏC�w���s������������\�肾�������A�L�����Z���ƂȂ����B
���x�̓y�E���̖����\����������L�����Z�����ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA�u�F�{�n�k�̉e�������ˁB�c�O������Ďd����Ȃ��ˁv�ƌ��𗎂Ƃ��Ă����B
�{���́u����V���v�ł��u�ό��w���]�L�̊�@�x�v�A�u�l�q��C�w���s�@�h���L�����Z���������v�Ƃ̋L�����傫���ڂ��Ă���A�F�{�n�k�����ȍ~�A���茧�ւ̊ό��q���������Ă���悤���B
�����ߏ蔽���ł͂Ƃ��v���B
���鎩���̂ł́u���S�ł��v���A�s�[�����ăL�����Z�����v���Ƃǂ܂�悤�����𑗂����Ƃ̂��ƁB
����ł��A���S�Ɉ��S���Ƃ͒N�������Ȃ��̂����A�s��������Ă����Ă��������Ƃ͌����Ȃ��̂��Y�܂����Ƃ��낾�B
�����������������ɑ�ς��ȂƎv���A���������邱�Ƃ͑����������F��̂ƍ����̊�t�����邱�Ƃ��炢�����Ȃ��B
�O��ɉ����A����܂Ŋւ��̂������ʂ̒c�̂ɂ����������t�𑗂����B
������́u���܃X�^�b�t�����n���肵�ăj�[�Y�����B��t�E�Ō�t�𒆐S�ɓ숢�h�������_�Ƃ�����Ê�������Ӓ����̈ړ��f�Â��s���\��v���Ƃ̂��ƁB
�O��̒c�̂́u�F�{���v�钬�ŁA�q�ǂ������S�E���S�ɉ߂������Ƃ̂ł����ԁw���ǂ��Ђ�x���J�݂����v�Ƃ̂��ƁB
�����{��k�ЂŔ�Q�������X���܂߁A�H���E�����E���N�E�R�~���j�P�[�V�����Ȃǂ����X�ɂł����S�Ȃ��̂ƂȂ��Ă����悤�F��B
���F �@ �S�{�E�͒��a7�p�A����20���p������H�ׂ��������邱�Ƃ��B



�{���̎��n �@�@�@ �肪�o���T�g�C�� �z�E�����\�E�̉�
�@�@�@�@�l�M�A�T�g�C�����܂ߐH���������Ԃ�Ɖ߂��Ă���̂����A����ł���ؑ@�ۂ�r�^�~���Ȃǂ̐ێ�ɂ͈���Ă���Ă���B
�@�@�@�@���N�̓C�`�S���ǂ�ǂ��Ă��Ă���B
���F �@ �T�g�C���̉�͂��킢���F�E�`���B
�E�F �@ �g�����Ȃ����炠���Ƃ����Ԃ�1���قǂ̏�ƂȂ�A�g�E�������ĉԂ��炢���B
�@�@�@�@���N�����͎���̂��Ă݂悤�Ǝv���B
�@�S�F �@ ����̌ߑO�̎ʐ^�B



����C�݁@1�@�@�@���l ����C�݁@2�@�@�@���i ����C�݁@3�@�@�@�m�l������u�ԑD
�@�@�@�@�m�l�̒�u�Ԃ̑D�͓�̊C�ō�Ƃ��y�����낤�Ǝv�����B
�@�@�@�@���l�́H
�@�@�@�@����̌ߌ�A�{���̌ߑO�͉_��Ȃ������������̂ɁA�_��Ƃɒǂ��ĊC�ӂ��U��ł����A���ʐ^���B��Ȃ������̂͂��������������c�O�B
4��21���i�ؗj���j�@�J�̂��܂�
��邩�獡���܂ł����Ɩ\���J���������B
�Ƃ̉�����������Ԃ̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ɂȂ�قǂ̕��A�����đ��ɑł�����J�B
�ߑO���͊O�ɏo�邱�Ƃ��ł����B�ߌ�ɂȂ��Ă���Ǝ~��ł��用�ɏo�Ă݂�Ǝ��͂Ɍ@���Ă���a�͐��т����B
�j���[�X�ł͑��J�ʂ�100�o�ȏゾ�����Ƃ̂��ƁB
�T�ԗ\��ł͓܂��J�������Ƃ̂��ƂŁA�앨�̍����ꂪ�S�z���B
�{���̍�Ɓ@�@
�u���̔��v�Ɓu���̔��v�̋ʃl�M�����B
3���̔����ׂĂ̖�A�ԁA�ʕ��ɍ؎���������{��B
���F �@ ����ڂ�����Y���S�{�E�̗t�B



�S�{�E�̗t �@�@�@ �p���W�[�@1�@�@�@�����O �p���W�[�@2�@�@�@������
�@�@�@�@��N�t�ɔd���A�āE�H�ɂ��������H�ׂ��B�̂��������̗t�͓~�Ɉ�x�͂ꂽ�̂����A�܂��萁���ĉh���A����1�����劔�ɂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�������̓X�J�X�J�̂��̂������H�ׂ�̂ɂ͂��܂�K���Ȃ��̂����A�܂��H�ׂĂ���B
�@�@�@�@���{�͎c���ĉԂ��炩���A����̂��Ă݂悤�Ǝv���B
���E�E�F �@ ����Ƒ���肪�ł����B
�@�@�@�@���Ɋ������Ɨz�͎˂��Ȃ����A�h�{���͎���邵�ʼnԂɌ��C���Ȃ��B
�@�@�@�@�؎���������T���Ă������B
�@�S�F �@ 19���̎ʐ^�B



���ǃ��l�@1�@�@�@�L���Ƃ�l ���ǃ��l�@2�@�@�@�L���Ƃ�l�@���i ���ǃ��l�@3�@�@�@�ٓV����
�@�@�@�@���ǃ��l�̍L�����l�ɐl����l�̂݁B�L�L�H�������Ă����B
�@�@�@�@�ٓV����݂͐̂͊���͂����Ԃꂽ�C�̒��ɂ���A���������Ȃ���Γn��Ȃ������悤���B���͌�ݍH�����s���A�قڔN�Ԃ�ʂ��Ă��Q��ɍs����B
4��22���i���j���j�@���ꂿ�܂�
�ߑO�͕��キ�������A�ߌ�͏��X�ɓ܂��Ă��ė[�������ڂ낰�������B
�{���͑�����g�}�g�E�L���E���p�̎x���p�̒|������B
��������5�C6���͓܂�E�J�̗\�B
�͂₭�W���K�C�����@��˂B
�{���̍�Ɓ@�@
�u���̔��v�̉Ԓd�̏����Ǝx�����āB
�X�C�J�A�������A�J�{�`���A�i�X�ɑ҂��N���c�L�i�����@���Ĕ엿����j
�L���E���A�g�}�g�̎x���p�̒|����
���F �@ ���ō̂ꂽ�S�{�E�A�j���W���A�j���W���̗t�A�T�g�C���A�ʃl�M�A�~���E�K�|�A����ɍw�������V���E�K�A�j���j�N�A�V�C�^�P�A�V���W�A�G�m�L�_�P��11��B



�{���̐H��11�� �@�@�@ �I�X�e�I�X�y���}���ƃK�U�j�A �J���[
�@�@�@�@�������Ƃ��ɎςĖ��X����ꂽ�B
�@�@�@�@3�������炢�̖�X�[�v�ɂȂ肻�����B
���E�E�F �@ ����������Ԃ�20���N�O�ɕꂪ�A�������́B
�@�@�@�@���������Ƃ����N���C�ɍ炢�Ă������̂��B
�@�@�@�@��Â���Ŗ�x���܂ł����������Ă�����X�������Ă��邪�A����ȉԂ̂悤�ȗ]�T�������Đ����Ă����˂�����ȂƎv���Ă����B
�@�S�F �@ 19���̎ʐ^�B



���㓇 �P���@1 �P���@2
�@�@�@�@���p�ŊX�ɏo���������̓r���̂悤���B
�@�@�@�@�������Ă��鍵�㓇�A�P����������ӂ��Ɍ����A������܂������G���Ǝv���B
4��23���i�y�j���j�@�܂�Ƃ��ǂ��J
���O����~���Ă��āA��܂Œf���I�ɑ������B
�҂�����50�N�Ԃ�ɏ��w�Z����̓��������W�܂�������A�X�̉��܂Ŏ��]�Ԃł����B
�J���~��������ł��Ȃ�̂��́A�E�L�E�L�C���ł̍s���A�肾�����B
�{���̍�Ɓ@�@
�u�O�̔��v�A�����̒|���́B
�u���̔��v�A�X�C�J�A�������̃g���l���̐��グ�i�c�ɂ�����Ȃ����x�ɉJ������j
50�N�Ԃ�̏W���i���w�Z�̓������W�܂�j
50�N�Ԃ�A���w������̓��������W�܂�������A10���l���W�܂����B
���̔N��ɂȂ�ƁA�����E�v�j�����߁A�����͂������o���ĕԎ����W�v���ĉ���\�āc�ȂǂƂ�����Ƃ��ł�����͂��Ȃ��̂ŁA���l�����A�Ȃ���̂ɍ��킹�ďW�܂��l���W���Ƃ����`���������B
50�A60�̓�����ʼn�����l�����邪�A�܂��ɑ��Ƃ�12����50�N�Ԃ�ɘb���Ƃ�������������B �i���w�Z��2�N���X�����������w�Z��6�N���X�ƂȂ�A���w����قǂ̐e�����͂Ȃ��B����ɁA���w���o�Ă��唼���W�c�A�E�������j
����ł���Ƃ����Ɂu���̓����A��v�ŁA�����̎v���o�ɉԂ��炢���B
�u���X�����A���A�͂�A�f�p�A�n�R�v�Ȃǂ̌��t���v���N�������ЂƎ��������B
�@�@�@�@�ȉ��͂��̎��̊F�̎v���o�Ȃ��̈ꕔ�B
�w�Z�ɋ߂��n��̐��k�͒��x�݁A�ƂɋA���Ă��т�H�ׂĂ���Ƃ����w�Z���j�������B
�e�͖�ǎd���ɏo�Ă���̂ŁA�N�����Ȃ��ƂɋA���Ďq�ǂ������Œ��H��H�ׁA�����ߌ�̎��Ƃɑ���Ƃ������ƂɂȂ�B
����Ƃ��A���̎q3�l�łP�l�̉Ƃɍs���A�n�K�}�ɂ��������т����炩���H�ׂ��B
�[���A�������e�́i�[�H�p�́j���т��Ȃ����Ƃɋ����A���������҂ǂ��������B
���̎q3�l�́A����A�����ƕ��܂݂�̋������̑|����������ꂽ�B
6�N���̂���A���鏗�̎q�������ݎq�̎q�������˂Ȃ炸�A�w�Z�ɗ���Ȃ������������B
�s�搶�͂��̎q������Ԃ��Ă��Ă���������Ƃɏo�ė����Ɛ��������B
�w����ꂽ�Ԃ�V�����鋳���ł̎��ƂƂȂ�A�Ԃ�����킢�������B
5�A6�N���̍��A���H�̎��ԂɒE���������o�����悤�ɂȂ����B
�܂����Ĉ��߂Ȃ������B
�s�搶������ŕ��R�R�A�̑�ʂ��ċ����ɒu���Ă��ꂽ�B
�������ꂽ�炨���������߂��B
�����A�NJw�K���͂��A�ǂ̒��ŋ��������悤�w�����ꂽ�B
�Z���̎��ƂŔǂ̎q���w������A�������Ȃ������B
�u�ǂ��Ĕǂ̑S���ł킩�肠���Ƃ��I�@�Z��1���I�v
�NJ����̗���s���̂������A�s���������������A�������킩���Ă��������́A
�u�搶�A����(��)������������Ƃ��ȁH�v
�u�����i�N���j���܂��Γ��ʈ�����������㌾�������I�v�Ɠ{���A�P�c�o�b�g�i���K�Ƒ������̊ԕt�߂��o�b�g�ł��������B�ɂ����]�V�ɂ��������������j�̂̂��ɍZ����������͂߂ɂȂ����B
���鏗�̎q�͑̈璅��Y��ăP�c�o�b�g�B�͂����ς���������ɂ������A�ƁB
���̓u���}�[�A��͕��i���ƌ����i�D�ő̈�̎��Ƃ���H�ڂɂȂ����B
�u�������ʂ����������āA����s�搶�͂悩�v���o����������B�@��������Ă݂����v�ƁB
���̂s�搶�A�w������̓��O�r�[������Ă����炵���M�����A������Ă̊�ŁA��ɂׂ̂��悤�ȏ�Ɍ����ʂƓ{��ƕ|���ʂƗ����������B
�Ƃڂ�����ʂ��������B
�搶�F�u�Ȃ��A�ܓ��ق��ᒹ����Ό�����A�����J�̑哝�̖̂��O�Ό�����ˁB�킩�����H�v
���k�F�u�H�H�H�v�i������������j
�搶�F�i�ˑR�A���̊O���w�����A�吺�Łj�u���A���V���I�v
���k�F�u�H�H�H�v�i�N���킸�j
�搶�F�u�������ƂΎn�ނ����v
�����A�����h�Z���������Ă���҂͂قƂ�ǂ��炸�A������|���铪�ɑ܂݂����Ȃ��̂Ŋw�Z�ɒʂ����B
���ꂳ���Ȃ��҂́A���ȏ��ȂǂC�~�ɕ�݁A�w���ɔ����čs�����B
���ȏ����Ȃ��̂ŁA�w�N�̏I���ɂ�1�w�N��̐l�̉Ƃɍs���A�ꎮ����������B
��������l�̖��O�������A�����̖��O�������ĐV�w�����}�����B
������܂��ʂ̐l�ɂ�����̂ŁA���N���g���Â���A���܂��������������Ă��鋳�ȏ��ɏo����Ƃ��������B
�`��~�J���͏n���̂��҂������������B
�Ђ������̂ƐH���Ӓn���͂��Ă���̂ő҂����ꂸ�A�ꂩ������a�������肵�Ă������߂ɍ̂��ĐH�ׂ��B�n��邱��ɂ͂����Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@�@�@�@1960(���a35)�N���w��1965(���a40)�N�x���ƁB
�@�@�@�@���{�͍��x�o�ϐ����̐^���������������̂��낤���A���̖L�����̗]�g�͂܂��ܓ��̔_�����܂ł͓͂��Ă��Ȃ������ȂƎv���B
�@�@�@�@�u���������Ă邤���͉�������ˁv
�@�@�@�@�u���̐��ł����i��j����A�܂����w�Z����b���悤�����v
�@�@�@�@�u�Ȃ�̌��C���Ƃ�A�܂����N����ł�A70�C80�ɂȂ������ł��������������v�Ȃǂƌ��������ĕʂꂽ�B
�@�@�@�@�y���������̔߂����A���������C���o���������B
�S�F �@ ��Ǝ��Ԃ������Ƃ����Ԃ�50�N�O�ɖ߂�B



���w�Z�����̏W�܂�@1 �@�@�@ ���w�Z�����̏W�܂�@2 ���w�Z�����̏W�܂�@3
�@�@�@�@����ȑ��ʂƁA�ł����ꂩ��50������d�˂Ă���Ƃ��������ƁB
�@�@�@�@�s�v�c�Ȋ��o�ŁA���ꂵ�����˘f����炾�����B
�@�S�F �@ �u���ǃ��l���t�����v�ɂ͒��w�����ŐA�������̋L�O��������B



���w�Z�����̏W�܂�@4�@�@�@���ǃ��l���t�����E������̋L�O���̑O�ɂ� ���w�Z�����̏W�܂�@5�@�@�@���ǃ��l���t���� ���w�Z�����̏W�܂�@6�@�@�@�A�H
�@�@�@�@�A�蓹�̓c��ڂɂ͂����c���A�����Ă����B
4��24���i���j���j�@�J�̂��܂�
�{����������J���f���I�ɍ~��A���O�ɂ���Ƃ�B
�ߌ�͐���̗\�������O��ē܂�����A�[���ɏ����������邭�Ȃ����B
�{���̍�Ɓ@�@
������̂����|�̉��H�i0.5��50�A1��50�A1.5��20�A2��15�قǁj
8�l�Œ���@�A����@�����
�����������w�Z�̓����́A�U��シ���D�ɏ���Ē���`�Ɍ��������l������A�����ܓ�������l���B
���l�����킪�Ƃ�K�˂Ă���A��Ƃ悭�U���R�[�X���ꏏ�ɕ������B
���ꂱ�ꏬ�w�Z����̎v���o�Ȃǂ���肠�������A�v�������Ȃ��b���B
�C�Ɉ͂܂ꂽ�ܓ��B�킪�O��y�����̐����ɂ��鏬���Ȕ����ŕ��������C�B
�ċx�ݒ��͖����C�ɐ����ėV�L��������A���w�Z�̓����͂���ł��j����Ǝv���Ă����B
���A�C���炿����Ɨ��ꂽ�W�����������l���́A�قƂ�ljj�������Ƃ��Ȃ��A�ƁB
���ł��j���Ȃ����A���ɓ���Ƃ����ɒ���ł��܂��A�Ƃ̂��ƁB
���Ƃ�����Ȏ��͔����o���A�߂��̎R�̒��ŗV�肨�ٓ���H�ׂĉ߂��������Ƃ�����A�ƁB
���w�Z�𑲋Ƃ��ďW�c�A�E�����̂��̌��݂܂ł̋O�Ղɂ��āA���߂Ă��b�����f�����҂������B
�����n���̍H��ɋ߂莞�����Z�𑲋Ƃ����̂��A���̒n�Ɏc�����蒷�茧�ɋA�����肵���������̘b�͋����[�������B
��Ƃ��̃R�[�X��������������ꂱ��ƌ��t�����킵���������A���Ĕɐ��Ƃ����قǂɂ���ׂ荇��������킯�ł͂Ȃ��B
��l�ŕ����Ƃ��͒��ق��A������ƕ@�̂��o����x�B
�{����8�l�ŕ������̂ŁA�悭�������悭��������ɂ��₩�������B
������܂��悵�A�̂������Ԃ������B
�S�F �@ ��Ƃ̎U���͂����������ŏ��̃|�C���g�������B



8�l�ł̎U��@1�@�@�@�J���R���I �@�@�@ 8�l�ł̎U��@2�@�@�@�A�U�~ 8�l�ł̎U��@3�@�@�@���㓇�ƃI�m�g�b��
�@�@�@�@�J���R���I��w�i�ɂ��āA�悭��̎ʐ^���B�����B
�@�@�@�@�{�����̕��i�����āA
�@�@�@�@�u�����N���ɂ����e���r�ɏo����i���B��������J���R���������Ă���f���������B�����������ˁv�Ɛ��������ꂽ�B
�@�S�F �@ �悭�����A�悭���A���w�Z����̉����C���ɖ߂��������������B



8�l�ł̎U��@4�@�@�@����@�ɂ� 8�l�ł̎U��@5�@�@�@����@�ɂ� 8�l�ł̎U��@6�@�@�@����@�ɂ�
4��25���i���j���j�@�܂�ꎞ����
����̗\��ł͍����E�����͐��ꂾ�������A�����̗\��ł͓܂��J�͗l�ɕς���Ă���B
�V�C���s����A�����������Ɍ������Ă���悤���B
�{���̍�Ɓ@�@
�u���̔��v�̃X�C�J�E���������Ƀr�j�[���g���l������B�v�u���̔��v�̃W���K�C���@��i5���j
�Ȃ������̈��́H�@�n�������H
�ӂƁA�Ȃ����w�Z����̎v���o�͂���ȂɂȂ������A�������̂Ȃ̂��낤�H�ƍl�����B
�n�R���Ђ��炩������͂Ȃ��̂����A
�F���n�����A���X�̐����ɖv�����Ă����䂦�ɁA���ꂱ��̂悫�ł����Ƃ��������C������B
�v���Ԃ�����A��������荇�����肵�Ă��A�S����Ȃ����݂�����B
�Ԃ�V�����Ԃ����q�����������A�E�������A�R�w�Z�i�T�{��j�A���H�ł̋A��c�B
���x�ݎ��ԂɋA��ł��Ȃ������̒n��̎q�͕ٓ��������čs���˂Ȃ�Ȃ��B
�����̏ꍇ�A��͔_��ƂŖZ�����̂ŕٓ��͎����ŗp�ӂ��˂Ȃ�Ȃ��B
�ٓ����ɔ��т��߁A�[�������Ē����͂�̎c�蕨������B
���������c���Ă��Ȃ��ꍇ�͖��X�`�̂Ȃ��ɂ���_�V�̃C���R�i�������j������B
�����Ȃ��Ă��A�ܓ���̎g����u�ӂ肩���v��������ꂵ�B
������Ȃ������قƂ�ǂŁA���̎��͂�������Ȃ��A���т������������Ƃ����������悤�ȁB
�u�߂��Ă��܂��݂Ȕ������v�I�ȁA�ߋ���������Č��Ă��鑤�ʂ����邩������Ȃ����A
�܂����w�Z����ɖ߂��Ƃ�����A�L���Ȑ�����肠�̐����̕��������Ǝv���B
�l�Ɋ��߂���A�����v���悤�������肷��C�͂Ȃ����A
�Ȃ��������̎�������Ă����Ƃ������킢���Ǝv���B
�S�F �@ �㉺6���̎ʐ^�Ƃ��u�O��y�@�O��y�����\���N�L�O�v�i1990�i����2�j�N���s�j���B

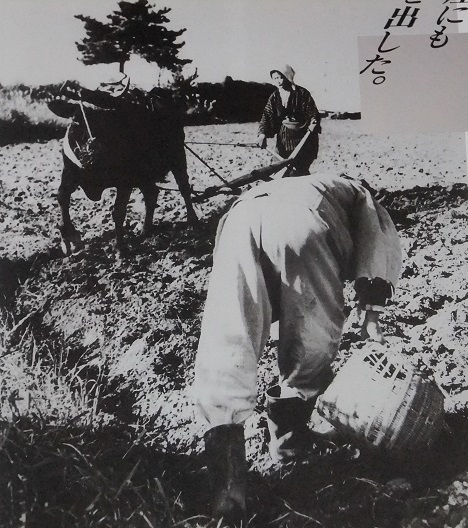

�̂̎O��y�@1�@�@�@�u���a30�N���A�J���R���؊����v �@�@�@ �̂̎O��y�@2�@�@�@�u���a27�N���A�C���̌�@��v �̂̎O��y�@3�@�@�@�u���a33�N���A���w�Z���ƎQ�ρv
�@�@�@�@���ׂĎ����̎q�ǂ����セ�̂��̂̏�i���B
�@�@�@�@����Ȏʐ^���c���Ă��邨�����ŋL�������N���ɂȂ��Ă��ꂵ���B
�@�S�F �@ ���������܂ꂽ����A1955�i���a30�j�N�ɂ�10,321�l�������l�����A1990�i����2�j�N�ɂ�4,935�l�Ɍ���A���݂�2,900�l�O��Ƃ̂��ƁB
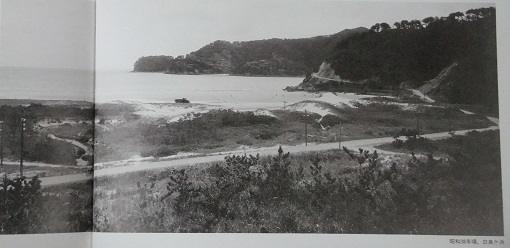


�̂̎O��y�@4�@�@�@���ǃ��l �̂̎O��y�@5�@�@�@���l �O��y�S�i
�@�@�@�@�E�̎ʐ^�̂���(1990�N���j�͂悭�k����Ă��锨�����i2016�N�j�͍k�삳�ꂸ�r��Ă��܂��Ă�����̂������悤���B
4��26���i�Ηj���j�@�܂�̂��J
�W���K�C�����@��I��˂Ɠ����ɓ���������������B �Ȃ�Ƃ���܂ō~�炸�A���ׂĎ��n�ł����B �傫�ȋʂ������悢�o���ł��ꂵ���B
�{���̍�Ɓ@�@
�u���̔��v�Ɓu���̔��v�̃W���K�C���@��i8���j�B�u���̔��v�Ƀc�N�l��A���i20�j�B�u���̔��v�Ɓu���̔��v�ɃV���E�K�A���i20�j
���E�� �@ ���N�̏t�W���K�C���͂܂��L��B



�W���K�C���@��@1�@�@�@�@��O �@�@�@ �W���K�C���@��@2�@�@�@�@������ �킪�Ƃ̑O�̐Ί_
�@�@�@�@��N�̎��s�����A���n�ȑ͔������̂���߂���A��C���Ǝ�C���̊Ԃɂ�����Ɣ엿��u���Ă݂��肵���̂��悩�����悤���B
�@�@�@�@����ɂ��Ă��A�S�̂ɂ͎{������Ȃ��������̃W���K�C���̓l�Y�~�̐H�Q���Ђǂ��B�������a�����߂̂悤�ȁB
�@�@�@�@����ɔ�ׂĐ��S�̂ɂ������엿�������Ă݂����͂����ł��Ȃ��B
�@�@�@�@�Ȃ����낤�B
�@�@�@�@�엿�����Ȃ����̃W���K�C�����������������Ȃ̂��A����Ƃ��엿���������������y�������Ȃ̂��B
�@�@�@�@�Ă��ĐH�ה�ׂ��Ă݂�ƁA�엿����������������F���Z���C�������B
�@�@�@�@�͂����āH
�E�F �@ ����̎ʐ^�B �K�U�j�A�͉����F�A�I�X�e�I�X�y���}���͎��Ɣ����s���N��2�킪�����Ă�����B
�@�S�F �@ ����̎ʐ^�B �����Ԃ�Ɨz���C�ɒ��ނ̂����Ă��Ȃ��C�����邪�A



�[���@1 �[���@2 �[���@3
�@�@�@�@����ȉ��₩�ȗ[�����܂��悵�B
4��27���i���j���j�@�J�ꎞ�܂�
�ߌ�ɂ�����Ƃ�����ȊO�͉J�����̈���B �ߌ�3�����납��͉J�͏オ��\�������t�ɋ��܂��Ă��Ė钆�܂ō~�葱�����B �܂�Ŕ~�J�̂悤�Ȉ���������B
�{���̍�Ɓ@�@
�u���̔��v�Ɓu���̔��v�̃\���}���A�ʃl�M�̎��n�B�W���K�C���̑I�ʁB�u���̔��v�Ƀg�E�����R�V�A���i90�قǁj
4��28���i�ؗj���j�@�i�J�̂��܂�F����j
�{�����قƂ�Lj�����J�B
�{���̍�Ɓ@�@
�u���̔��v�Ƀg�E�����R�V�A���i40�قǁj�B�u���̔��v�Ɓu���̔��v�ɃY�b�L�[�j�A���i7�j
�� �@ �\���}���A�ʃl�M�A�W���K�C���B



�{���̎��n �@�@�@ ���r���O�X�g���f�[�W�[ �H�ƃO���W�I���X
�@�@�@�@���炭�o������̂ŁA�������߂̊������邪�\���}�������n�����B
�@�@�@�@���V�s���Q�l�ɐ�1���b�g���ɉ��傳��2�t�A��100�t��2����䥂ł�B�����킢�Ƃ������t�̖����Ɗ�����B
���E�E�F �@ �O���W�I���X�͕ꂪ�A�����̂����������ɌQ�����A�炢�Ă���B
�@�@�@�@���F�́H�������͂������A�����Ă����ǂ�ǂ��������B
�@�S�F �@ 4��9���̎ʐ^�B



��ܓ��@1�@�@�@�ᏼ�� ��ܓ��@2�@�@�@�ᏼ�� ��ܓ��@3�@�@�@���ʓ�
�@�@�@�@���ܓ��E�v��̊C�̐���\�����āA�v��u���[�Ƃ������t������炵�����A�����̓��̊C�̐F�����ꂢ�Ȑ[�E���F���B
4��29���i���j���j�@�i����F����j
�i�݂��ƂɈ��������B�����̓y�A��������}�[�N�̂݁j
�� �@ 25���̎ʐ^�B



�{���̎��n �@�@�@ �W���K�C��3�� �H�N��
�@�@�@�@�C�`�S�͂�����ŐH�ׂ����A���͓����Ⴊ�ɂ��Ă����������B
���F �@ �ʐ^���͂��ꂢ�ȃW���K�C���A�^�͓y���Ńl�Y�~�ɐH�ׂ�ꂽ���́A�E�͂������a�̋ʁB
�@�@�@�@���ɔ엿���{���Ȃ��������̕����l�Y�~�ɐH�ׂ��Ă���͕̂s�v�c�Ȃ��Ƃ��B
�@�@�@�@�������a�̓C���̕\�ʂɒ��F�̔��_���ł�����́B���⌒�N�E�h�{�ɂ͖��Ȃ��Ƃ̂��Ƃ�����͂茩�h���������B
�@�@�@�@���������͂Ȃ��̂œ���Y�܂��قǂł͂Ȃ����A�A��������A�A���t���O�ɐΊD���T���A���ⓤ�ނ̗Δ����Ă���̐��ɐA���t����Ȃǂ̑�����Ă݂悤�Ǝv���B �E�F �@ ���̃N���͂킪�ƂœV��A�ǁA��̏�Ȃǂ����������܂���Ă���B
�@�@�@�@�p�������͂��킢���Ƃ͂������A�O���e�X�N�Ƃ������|����������B
�@�@�@�@���A��⃀�J�f�ɔ�ׂ�ΐl�Ɉ��������邱�Ƃ͍��̂Ƃ���܂������Ȃ��̂ŁA���܂�C�ɂ����U���Ă���B
�@�S�F �@ 3��17���̎ʐ^�B



�I�m�g�b���@1 �I�m�g�b���@2 �I�m�g�b���@3
�@�@�@�@�����Ɩ����E������͐����F�B
�@�@�@�@�����Ƃ���Ȍ��i���낤�B
4��30���i�y�j���j�@�i����F����j
�i���������������j
�S �@ 4��20�A25���̎ʐ^�B



�킪�Ƃ̃[���j�E�� �@�@�@ �ߏ��̉Ԏ�{�E�J�[�l�[�V���� �ߏ��̃K�U�j�A
�@�@�@�@�킪�Ƃł����ߏ��ł��Ԃ����肾�B
�S�F �@ 3��21���̎ʐ^�B



���̓���@1 ���̓���@2 ���̓���@3
�@�@�@�@���̓��̗[���͊ۂ��܂܊C�ɓ����Ă������B
�@�@�@�@�������ɐG�ꂽ�Ǝv����3���قǂŒ���ł��܂��B
�@�@�@�@�����Ƃ����ԂŁA���키�ɂȂ��A���B
���g�b�v�ɖ߂�