���g�b�v�ɖ߂�
3��1���i���j�J�i����j�@�@�@������J�͗l�ŏ��X�ɋ����Ȃ��Ă�����܂Ŗ{�i�I�ɍ~�葱���܂����B�@�@�@�O�ɋ߂Ă������Z�̑��Ǝ��ɏo�Ȃ����Ă��������܂������A�e�䂳���͉J�ő�ς����ł����B�������A���Ɛ������͎��ŁA���̌�̉�Ő��C���ӂ��M��������Đ����o���A�̂��A���đ������Ă��������������܂��B�ی�҂̕��X���g�����n���̖�o���j���Ă���A�������ł����B
�t��E�搶�i��C�M���u�̉Ԋ��v�j�@�F�@ �@�{���A���Ǝ��̋A��ɖ�C�M���u�[���̗̌��v�i���M�I�j���́u�̉Ԋ��v��ǂ�ł�����A���R�u�搶�v�ɂ��Ă̈ꕶ���������B�@�@�@�u����Ƃ͎t�킪�e��������ڂ��A���Ȃ�Ƃ���̂��̂��炨�̂����甭���邲�Ƃ������ł����đ��킽�邱�Ƃł��낤�B�̂��p�������߂�悤�ɐ������鍰�͌��t�̖{���̈Ӗ��Łw�搶�x�����߂���̂ł���v�@�@�@�ݐE���A����ȁu�搶�v�ɂȂꂽ�Ƃ͌�����Ȃƌ��߂������������A��C�����ȉ��̂��Ƃ������Ă����B�@�@�@�u�Ƃ��낪�A�t�Ƃ������t����q�Ƃ������t���A����ł͎���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂����̌��O�ł���B���w�⍂�Z�ŋ����Ă��鎄�̗F�l�́A���̌��O�ɑ��A�����Ԃ��Șb���Ƃ����B�������ׂĂɗD�悷�铖���ŁA�t��̌����ȂǂƂ����͎̂�����낾�Ƃ����̂ł���B�܂��߂ȋ��t�قǔ����̓x�������B���̐l�����̔M�S�Ȏd���Ԃ�����m�蔲���Ă���̂ŁA�����������̂��낤�Ɣ[�����鑼�͂Ȃ��B�����A�搶�����͎��ɓ���Ŏd�������Ă���̂ł���B�����̓����O�������������ł��������a��\�N��㔼�Ƒ傫���ς���Ă��܂����B���������ɂ͓s��ł���c�ɂł��ꏭ�N�����Ƌ��t������Ƃ���ɂ͕K���w�O�r�x�i���w���t�E�ɓ��×Y�Ɛ��k�E���쏁�O�Ƃ̎t��W��`�����A����ɂ�鏬���j�ɕ`���ꂽ�悤�ȍK���Ȏt�킪���g���͍������݂��Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��v�@�@�@���̕��������ꂽ�̂�40�N�O��1975�N�i���a50�N�j�ł��邯��ǁA���݂ɂ����̂܂ܓ��Ă͂܂�̂ł͂Ȃ����Ɗ������B�@�@�@
���E���@�F �@ �����ȑ��Ǝ��̂��Ə����x�e���Đ��k�̎�Âɂ�邨�ʂ�̉�Â��ꂽ�B�e�䂳���̑O��3�N�Ԃ̍��Z������s���̂悤�����X���C�h�V���[�ŗ�������A��\���e��搶���ւ̊��ӂ̌��t���q�ׂĂ����B�Ō�ɂ͕ʂ�̉̂�S���ō������ďI���A�f���炵�����Ԃł����B�@�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ ����ɗ���r���ɂ��������́B�u�S���݂����@�@�m�b���͂����ށ@�@�̂���������v�@�V���v�������A���w�Z���獂�Z�A��l�ɂȂ��Ă������������悢�ڕW���ȂƊ����܂����B�������A���ꂪ��������ɂ͎Љ����A�n���e�̃T�|�[�g���K�v�Ȃ̂͌����܂ł�����܂��B


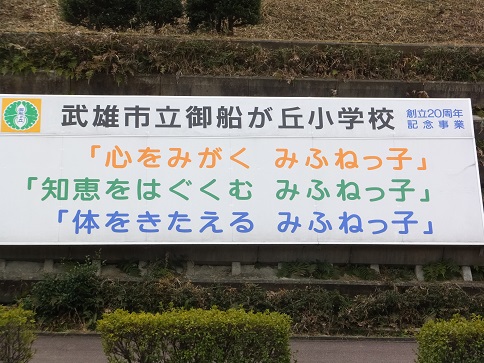
�r���Z�A���Ǝ���̂��ʂ�̉�1�@�@�@���Ɛ��S���ɂ��ʂ�̉� �r���Z�A���Ǝ���̂��ʂ�̉�2�@�@�@���� �l���w�Z�̕W��
3��2���i���j�����i����j�@�@�@�_�͂قƂ�ǂȂ��ŁA����̑�J�ƑΏƓI�ł��B�@�@�@1�̑���A��ė���́u���a�L�O�����v���U��B�t�N�W���\�E�A�X�C�Z�����o�n�߂Ă���A�E���͖��J�B����ɂ��Ă��A1�Ύ��̔���m��Ȃ��������A������V��ł̗V�тɂ͋�������ł��B�����āA������ꂽ�炠���Ƃ����Ԃɖ����Ă��܂������ɂ��E�X�ł��B
���ꂪ���̕���i�f��u���C�t�E�C�Y�E�r���[�e�B�t���v�j�@�F�@ �@�{���̂a�r�ł��̉f�悪���f����Ă����B�@�@�@�C�^���A�̂���X�ŏ��X���c�ރ��_���n�̉Ƒ����������e���ɓ������B���ƕ�Ǝq�̂���ȑO�̐�������e�����ł̂悤�������[���A�������ĕ`���Ă���B��]�Ɨׂ荇�킹�̂Ȃ��ŌJ��L�����郆�[���A�ł��邽�߁A�ςĂ��ċt�ɂ炳�������Ă��������������B�@�@�@�ڂ̑O�̌����͔ߎS�Ŕ�l�ԓI�Ȃ��̂ł��邯��ǂ��A�q�ɂ͐l�������邭���������̂Łi���j���邱�Ƃ�m���Ăق����Ɨ܂��܂����w�͂��������镃�̎p�ɂ͋����l�܂�B�@�@�@1999�N�̌��J�̎��ɊςĈȗ�������14�C5�N�Ԃ�ł���B�����̒��̃x�X�g�̉f��͑�ł���䂦�ɊԊu���ĐS�̓��Ŕ��y�����Ă��������悤�ȁA����p�ɂɊς����悤�ȕ��G�ȋC�������B�@�@�@�f��̍Ō�̏�ʁA�q���u���ꂪ���̕���v�ƌ��V�[���ł́A�v���������Ƃ�������͂�Ƃ������������Ă��܂����B�������A�����݂݂̗̂܂łȂ������̂͂��ꂵ�����Ƃł��B�@�@�@
���@�F �@ �@���͓y�݂̂ł����A5�����ɂ͐F�Ƃ�ǂ�̃`���[���b�v�ŊG�̂悤�ɂȂ�܂��B�@�@



���a�L�O����1�@�@�@�X�C�Z�� ���a�L�O����2�@�@�@�`���[���b�v�� ���a�L�O����3�@�@�@�Ԃ���
���@�F �@ �@����1����������A�Ƃ����ɏI������E����O�ɂ��ĉ��̃T�N�������J�Ȃ̂ł��傤�B�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ �t�N�W���\�E�͓y�������o��������̉Ԃ��肪���ł��܂����A���̐��N�A���̌�̗t�̐����̂悳���܂����͂�����Ɗ����Ă��܂��B



���a�L�O����4�@�@�@�g�~�ƃP���L�̖� ���a�L�O����2�@�@�@���~�ƃT�N���̖� ���a�L�O����3�@�@�@�t�N�W���\�E
3��3���i�j�܂�i����j�@�@�@�Ƃ̕�C�⏰�̃��b�N�X�����A��̎����Ɋ��𗬂��B
���Y�O���A�M�ɏ��i�u���{��\�Z���l�@��D��Ձv�j�@�F�@ �@���̂g�o��26���ɋL�������ދn�����j���������ق̂��̈ē��Ɂu���{��\�Z���l�@�o�`�̒n�v�̕������������B�����ĊC�̕���2�C3�������Ɓu���{��\�Z���l�@��D��Ձv�̔肪�������B�@�@�@1597�N�i�c��2�N�j2��4���A26�l�͂�������3�z�̑D�ɏ悹���đΊ݂̎��ÂɌ������A�����A����̐���Ŏ��Y�ƂȂ����Ƃ̂��ƁB�@�@�@�ނ�̓L���X�g�����߂���������ׂ������̃L���V�^�����������߂ɂ��悤�ƍl�����L�b�G�g�̖��ɂ��A1��9������k���ł��邢�͔n�ō�A�P�H�A���R�A�L���A�����Ƃ������Ƒ����A1�����߂��������Ă��̒n�ɒ������B�@�@�@�����܂łǂ�ȗ��H�������̂��A���̒n����D�ɏ��Ƃ��ǂ�Ȏv���������̂��B�������ɂ́A�u��ɂ́A�c��������n�߁A�݂̂��������ɋ����̓����܂������A�M�́A�P���ȘE�̉��������������Ȃ���A�Â��ɐ��ʂ��Ă������v�Ƃ���B���̏�i����ї����̂��Ƃ�z������Ɣw�������Ȃ�܂��B�@�@�@���Ƃ́A���Ƃ͎��Ƃ͐M�Ƃ́B�厖�Ȃ̂����A�}�l�ɂ͐[�����ēr���œ˂��l�߂�̂��~���Ă�����������܂��B�@�@�@�@�@�@�@
�S�@�F �@ �@�����`�ƌ�����{�݂͂Ȃ��B�����Ȑ�̉͌��ɓy�����͐ς����ӏ��ŁA���낤���ď��M���q�����葆���o������ł���ꏊ�������悤�ł��B�@�@



�u���{��\�Z���l�@��D��Ձv1�@�@�@�㗬�̋����̉��] �u���{��\�Z���l�@��D��Ձv2�@�@�@���]�� �u���{��\�Z���l�@��D��Ձv3�@�@�@�L�O��
�S�@�F �@ �@�����26�l���D�o�����̂Ɠ���2���̏�D��Ղł��B���C�ł���呺�p�͓���������ȋ��̂悤�Ȑ��ʂɋ����̓����f���Ă����̂ł��傤���B�@�@�@���̗\���m�����Ȃ��A���R�ɂ��̒n��K�˂��̂ł����A400�N�ȏ�O�̓����̂悤�����Â����i�ł����B�@�@



�u���{��\�Z���l�@��D��Ձv4�@�@�@�쑤�̑͐ϒn �u���{��\�Z���l�@��D��Ձv5�@�@�@����]�� �u���{��\�Z���l�@��D��Ձv6�@�@�@����]��
3��4���i���j�܂�̂�����i����j�@�@�@���l�A���ؒ�����R�������܂ŊC�ӂ�����B40�N�قǑO��20�̍��A�ܓ����牡�l�ɓ����ɗ�������A��Ђ̐V����É��o�g�̐�y���炱���ɘA��Ă��Ă��炢�A��̉��l�̕�����Љ�Ă����������̂����������v���o���B
�y�ɟ��݂��H�C�ɏ������H�i�����̗��@�u����Ձv�j�@�F�@ �@1637�N�i���i14�N�j�A�u�����̗��v�̋��_�ƂȂ�����B�@�@�@�L�n���ɑ����ē����ː���S�������q���̖͗��ɉߍ��ȕ����Əd�ł��ۂ��A�L���V�^���e���Ȃǂ��s�������ߓV���l�Y��Ƃ��Ă��̗������������B���͂R�q�A�S�P�������q�Ƃ����L��ȃG���A�̏�i�Ձj�ɂR���V��l�Ƃ�������l�X���R�������̂������ď邵�A�唼���E�Q���ꂽ�Ƃ̂��ƁB�@�@�@�ď�Ɏ������o�܂⏗�q�����܂ޕS���������������Ƃ�m��ƁA�����̔����v���܂��B�@�@�@�u�p�Y�����̑I���@�@���ˁI�����̗��v�Ƃ����e���r�ԑg�ł́A�V���l�Y��S�������͔j��E���ꂽ����ǂ����{��e�˂͂���ȍ~��ȏd�ł��ۂ����Ƃ��T����悤�ɂȂ�A���N�v�����[�߂�ΉB��ăL���V�^���M�������Ƃɂ��ڂ��ނ��Ă����悤�ł�����A�Ƃ̃R�����g���������B���̈Ӗ��ł͕S�������͏������ƌ�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��B�@�@�@�����Ȃ̂�������Ȃ��Ƃ��v���B�������A���̏����H�邽�߂ɕ������]���͂��܂�ɑ傫���Ɗ�����B�@�@�@�@�@�@
���@�F �@ �@�ď邵���G���A���ɂ͍��������̔����c���Ă��ċʃl�M�A�u���b�R���[�Ȃǂ���ĂĂ��܂��B���E��Y�ɓo�^���ꂽ�炱���̔��͂ǂ��Ȃ�̂��낤�B���낢��Ƃ���܂ł̌o�߂͂��邾�낤���A�������\�N���S�N�k�삵�����Ă���Ƃ�����̂܂ܐ��Ƃ𑱂���ꂽ�炢���Ǝv���܂��B�@�@ �@�@�@���@�F �@ �@�{�ۂ̓��A�쑤�͊C�ɖʂ������\���̋}�s�ȊR�B�K�ꂽ���͔g�������Ȃ�䩗m�ƈÂ߂̊C�ŁA�R���Ղ��ɂ�3�̂̂��n������炵�������C��]��ł��āA���������̂����̂P�̂͏\���˂�����Ă��āA�Ȃɂ���邹�Ȃ���C�̕���ł����B�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ �@���{�̈ӂ��������R�́A�ď邵�Ă����l���E�����������ł͂܂��s���������̂ł��傤���B�{�ۂȂǂ���d�ɂ��͂�ł������S�ȐΊ_��˂������A���ɗ��Ƃ��ēy�Ŗ��߂Ă����Ƃ̂��ƁB�������E�����l�X�̈�̂��ꏏ�ɖ��߂Ƃ̂��ƁB�@�@



�����1�@�@�@�k�����{�ېՂ�]�� �����2�@�@�@�{�ېՂ�蓌���ʁA�L���C��]�� �����3�@�@�@�Ί_������A���҂̍�����Ƃ����߂Ă�����
���@�F �@ �@�ď铖���͂����ɘm�Ԃ��̌@�����������āA���E�q���E�V�l���Z�܂킹�Ă����Ƃ̂��ƁB�@�@ �@�@�@���E�E�@�F �@ �@��X�Θp�ƕ����A�V���������N�g�߁i�N�A�g���E���K�b�c�B�j�̈�l�A��X�~�Q���������т܂��B�����A���̋߂����ނ̌̋��ł���Ƃ̂��ƁB�@�@�@�Ȃ��A400�N�O�̗��j�����ǂ����悤�ȍs���ł����B�@�@



�����4�@�@�@�{�ۋ߂��̋�x�B ��X�Θp�i�k�p�j1 ��X�Θp�i�k�p�j2
3��5���i�j����i����j�@�@�@�_���܂�����A�����Ƃ͂������B��Ă��锨�ɃW���K�C����A����B
�̂������ς��ʂ��́i��C�M���u�|���Ҋ����L�v�j�@�F�@ �@����قǂɐ�捂ł����Ƃ�Ƃ��������ɏo������̂͋v���Ԃ�ł���B����ȖڂŎv���Ԃ��Ɠ�������u酂�J�v�u�����̂�����v�A�R�{���ܘY�u�ׂ�����v�A�V���g�����u�݂����݁v�Ȃǂ������Ԃ��A�����ɈႤ�悫���킢������B�@�@�@���e�̓y���[���q������|���˂�ɉ������m�̖��̖ڂɉf�������퐶����`�ʂ������́B����瓇�˂̎x�˂Ƃ��Ď��D����ˎ�̊قł������ł͂Ȃ��J�������ł���悤�ȕn�R�˂ł�����h����^���h�~�̓y�؍H���ȂǏo��͂����ވ���ł���B����Ȓ��ł��A���X�̐����͐Â��ɗ��������̂����b�Ői��ł����B�@�@�@�������炭�́A����̑�2�̌̋��A���茧�|���ŏ�����������C�M�����̖{���J�����Ƒ����B�ނ͐̂ƍ��̐����͕ς�����悤�Ɍ����Ă��l�̊�т�߂��݁A�������̎��͕ς��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�ƕʂ̐��M�ŏq�ׂĂ����B���̎v�����Ïk���ꂽ���삾�Ɗ������B�@�@�@�@�@�@
�S�@�F �@ �@��������܂������A40�N�߂��O�ɉ�Ђ̐�y�ɘA��Ă��Ă�������̂����߁B�̋��̌ܓ��ŋ��D���Ƃ���4�N�ԉ߂����A19�ŒN���m�荇���Ȃǂ��Ȃ����l�ɗ��ĐS�ׂ��������X�̍����ԁA�������猩����C���y�̍D�ӂ͋C�����������Ă��ꂽ�B���ӁB�@�@�@����Ȍ����l�ŁA��l�ŁA�q�A��łƐ܂ɂӂ�ĖK��Ă��邪�A�����Ă�����������炰�A�������������Ă����ꏊ�ł��B�@



���l�@�R������1 ���l�@�R������2 ���l�@�R������3
���E���@�F �@ �@�N���b�J�X�͂��̌����Ő��̑w��˂��j���ĉ���o���炢�Ă��܂��B���ȉԂɎ����킸�A����Ȃɂ����������͂������Ă���Ə��߂Ēm��܂����B�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ �@�C�ۗ\��m�̌��t�ɂ��A�{����1�N�ł�����n���ƌ������������Ƃ̂��ƁB�f���炵�������ł��B�@�@



���l�@�ԃ����K�q��1 ���l�@�ԃ����K�q��2 ����@��N�ň�ԏ�������
3��6���i���j�܂�i����j�@�@�@�����������芦���B����ł����͌����𑖂�������{�[���𓊂��Ă͒ǂ���������Ɣ���m��ʓ����ł��B
������Ƃ������Ƃ́@���̂������Ƃ������Ƃ́i��C�M���u�[���̗̌��v�j�@�F�@ �@���̐��M�I���́u�ꖇ�̎ʐ^����v�Ɉȉ��̌��t���������B�u���̂������Ƃ������Ƃ͒��x�̍��������ꂷ�ׂĉߋ��̕����ł���B���͂ɂ���Čo�����Ċm�F���邱�Ƃ��Ƃ�����������悤�ł���B���̌��ʂ͂����肷��̂́A�������ǂ̂悤�Ȑ��E�Ɉʒu���Ă��邩�Ƃ������Ƃ��B�������ĉߋ��̂��鎞�Ԃ��Č����Ȃ��猻���ɂ͍��̐��E���Ă��邱�ƂɂȂ�v�@�@�@�@�v���Ƃ��Đ��M�⏬���������Ă���l�͂���ȑz���ŕM���Ƃ��Ă���̂��Ǝv�����B����ȃG�L�X�𖡂�킹�Ă�����Ă���ƍĊm�F�����B�@�@�@���̐��M�͈ȉ��̕��ŏI����Ă����B�u�i���܂�Ă��a�J����܂�8�N���߂���������A�����𗎂Ƃ��ꂽ����@�@�Ǘ��l�j�n�ォ����������̌̋����L���̒��ɂ͑N���ɐ����Ă���B�|�p�Ƃ͋L�����A�Ɖp���̂��鎍�l������Ă���B�Ȃ�ł���₿�����������Ƃ������̂̂Ȃ����ɏ�������������͂��͂Ȃ��B�����Ƃ͎��ɂ��Ă����Ύ��̎��������̑S���Ƃ������ƂɂȂ�B���A���N����A�ƒ�A�F�l�����B������Ƃ������Ƃ͂����̂��̂�₦�������Â��邱�Ƃ̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��v�@�@�@42�i1980�N�j�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ�Ȃ���A���̎v���ŏ����ꂽ�u���́v�������Ɠǂނ��Ƃ��ł����낤�Ɏc�O�Ȃ��Ƃł��B�@�@�@�@�@�@
���@�F �@ �@�����ł́A�^�~�ɍ炭�E���Ə�̃}�c�A�^�P�����킹�āu�Ί��O�F�v�i����Ȏ��ł��ς��Ȃ��e�������F�̈Ӂj�Ǝ]�����Ă����Ƃ̂��ƁB�܂��A���{�ɂ͌����g�̎���ɓn�����A�������ケ��܂ł͉Ԍ��̎���Ƃ��Đe���܂�Ă����B�T�N��������ɂȂ����̂͂��̂̂��Ƃ̂��ƁB�@�@�@����Ȉ����m��ƁA���ł�ڂ��܂�����Ă��܂��B�@ �@�@�@�E�@�F �@ �@�ܓ����X�ł̓}���`������g���l�������ĐA���A�����肪�o����傫���Ȃ��Ă��锨������܂��B�@�@�@����A�������̎�C���̉肪�n��ɏo��̂�4�����߁A���n��6�����߂ł��傤���B�@



�E�� �ă~�J�� ����ŐA������W���K�C��
3��9���i���j�J�̂�����@�@�@����Ă����������A�k���銦���ł��B�\��ł͓���͍ō��C��13���Ȃ̂Ɍܓ���6���A���̂���������\���܂����̕��������Ƃ̂��ƂŁA��͏k���܂肻���ł��B
�E�O�C�X�����@�F�@ �@�J�����W�߂Ă�����߂��̃��u���炠�̉������������B3�����{�ł͂܂��܂������낤�Ƃ킪�����^�������A���x���J��Ԃ���������̂ŊԈႢ�Ȃ��B�@�@�@�����͋}�Ɋ����Ȃ肻���œ~���߂��Ă����������邯��ǁA�ԂⒹ�����ɂƂ��ďt�͊m���ɂ��Ă���悤�ł��B�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�J���W��
���@�F �@ �c�}�~�̉Ԃɉ����A���x�̓J�u�̉Ԃ����J�ɂȂ��č̉Ԃ̒��ԓ���ł��B �@�@�@���E�E�@�F �@ �킪�Ƃ͉��F���X�C�Z���i���m�X�C�Z���H�j���唼�ł��낻�됷����߂�����������܂����A���x�͔����X�C�Z�����炫�n�߂Ă��܂��B���[�ɍ炢�Ă��锒�X�C�Z���͉Ԃт�̒��̕����i���Ԋ��j�����F����ށi�j�z���Y�C�Z���H�j�������̂ɁA�킪�Ƃ͕̂��Ԋ������ł��B���m�X�C�Z���Ɠ��{�X�C�Z���̎G��ł��傤���B����Ȏ�ނ����邱�Ƃ����߂Ēm��܂����B



�ʘH���ӂ����قǐ��������̉ԁi�˖�J�u�j ���X�C�Z�� ���X�C�Z��
�S�@�F �@ �����͂����ƍr��āA���z���˂��Ȃ�����̂悤�ŁA���܂����X���X�ł��B



����@���� �I�m�g�b������1 �I�m�g�b������2
3��10���i�j��̂��܂�@�@�@�����͕��Ⴊ�����A���\���œ~�̗��̍ė��Ƃ��������ł����B�ߌ�͏��������܂������A����ł������Ŋ�������ŁA���������L�т��W���K�C���̗t���k���܂��Ă��܂��B
���H�@����H�i���̐��ŕ��́j�@�F�@ �@��������ɍ��i�����Ƃ̒m�点����B��ɓ`����ƁA�u���[�A�悩�����ˁB�悩�w�Z���H�v�ƁB�u����[�A���{�ŏ��߂Ăł�����w�����v�Ƃ����ƁA�u����A�����B�K���o���ĕ�����ˁv�ƒW�X�������B�@�@�@���������܂�ǂ߂��A���^���ꎩ���ԖƋ��i�k�^�@�p�j���Ƃ�ɍs���������u�W���ɖ��Α傫�Ȑ��œǂ�ł��낤�ĂƂ����������v�ƍ��ꂵ�Ă������́A���̐��Ŗ��ΎO�����A����Ƃ��u�悤���܂��A����������ˁ[�v�Ƌ�����B�@�@�@�Ƃ�����A���Z���w�̍��i�̒m�点�����������ŕ������Ă��܂��B��̌������Ƃ��A�ǂ̊w�����u�悭�w�сv���悭�V��ŁA�悫�w���������߂����Ăق������̂ł��B�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�J���W��
�S�@�F �@ �L���x�c�̉Ԃ̓L���x�c�����n������ɘe����Ԍs��6�C7�{�o�Ă��܂��B�J�Ԑ��O�̌��C�ȕ���Ȃ̂ŁA���Ђ����ɂ���̂͂�߁A�Ԃ����ł悤�Ǝv���܂��B



�n�N�T�C�̉� �L���x�c�̉� �q���V���X
�S�@�F �@ �Ƃɂ������ɂ������r�ꋶ���݂̂̊C�Ƃ�������ł����B�ʐ^�͌ߌ�A�����g�������܂������̂��̂ł�����A�ߑO�͂����Ƃ����������̂��낤�Ǝv���܂��B



�P�� ����@ ���㓇
3��11���i���j�܂�̂�����@�@�@����̗��Ƃ͑ł��ĕς���ČߑO�̑����������琰��A����ɂ��������o�܂����B�@�@�@�䂪�Ƃ̔��ɂ��Ă��E�O�C�X����������Ă���A�����芦�����Ԃ�Ԃ��Ȃ�����A�t�̐����͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B
�����A�����i�����{��k��4�N�ځj�@�F�@ �@�킪���ł��ߌ�2��46���A1���Ԃ̃T�C����������B�����Ď�����킹��A�����Ȃ��B�@�@�@�u�N���[�Y�A�b�v����@�@�ӂ邳�ƂɋA�肽���E�E�E�@��������4�N��̕����v�ł́A�Q�]���̏Z���̂����u�߂肽���v�Ɠ������l�͐k�В����64%�����݂�17%�Ɍ������Ɠ`���Ă����B���߂�邩�킩��Ȃ��A�߂�邱�Ƃ����܂��Ă��W����R�~���j�e�B���������邩���ʂ��������Ȃ��䂦�̐����Ȃ̂��낤�B�@�@�@����̓��_���i�����j�̍��w�r���ɏZ��ł��邠��v�w�����҂��Ō��Ă��Ƃ́A���͓D�_�ɍr�炳��A�l�Y�~�A�C�m�V�V�A���A���Ȃǂ����荞��ŋ����Ă����B���܋A��Ȃ��ƌ��߁A�Ƃ���̂���Ȃ�⏕�����o��Ƃ̂��ƂŁA��l�͋�a�̖��u�A��Ȃ��v�ƌ��߁A��̊�]�̏��ނ��o���Ă����B�������A�u�����ŋA��Ȃ��ƌ��߂Ă��A��͂�A�肽���ł��v�u�����͖�i�����{�ꂫ�ꂢ���ƌ������ǁA�ӂ邳�Ƃ̃|�c���|�c���Ɠ_���Ă���i�F�̕����D���ł��v�Ƃ̌��t�����̋�������Ă���Ɗ������B�@�@�@���N�̍����́A���▾���͂��悢���ɂȂ��Ă��Ăق����ƋF��܂��B�@�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�Δ�̊�����B�\���}���̎x������
���E���@�F �@ �H�ɂ��ڂ�킩��肪�o�A�~���z�����q�}���������{�炢�Ă��܂��B���͂ŐL�т��Δ�i���j���k�������������Ă��ꂽ����ł��傤���B����ɂ��Ă������������͂ł��B�@�@�@�Δ�������ăX�b�L�������̂͂悢�̂����A�t�̗��Ń|�b�L���܂�Ȃ����Ƃ��肢�܂��B �@�@�@�E�@�F �@ ���̂ǂ��ɂ��Ă����Ă���B�����ō�Ƃ��Ă���Ə����̒��ɂ܂œ����Ă��ċ߂��Ɋ�����藣�ꂽ��`�[�`�[�Ƃ��������Ă��܂��B�܂Ƃ��������ł͂Ƃ������܂����A�����Ƃ������Ƃ������o�͂܂������Ȃ��B������u���C���H�@�����Ό@��������A�~�~�Y�ł��T���Ă݂�v�ȂǂƐ����|����ƁA������𒍎����������X�����肷��̂ʼn����S�{�ł��B



�Δ�̊�����1�@�@�@�O �Δ�̊�����2�@�@�@�� �W���E�r�^�L
�S�@�F �@ ����ɔ�ׁA����C�����₩�ł��B



�P���Ɖ���@ ���㓇 ���㓇�ƒ���@����
3��12���i�j�ɂ킩�J�̂�����@�@�@�ߑO9���O��ɋ��߂̂ɂ킩�J��10�����~�����ȊO�͐���B�ߌ�͉����ɋ߂��Ȃ��ĉ߂����₷���B�Ƃ͂����A��̒n�\���x�̓}�C�i�X2���B����4���������̂ŕ��˗�p����ڗđR�ł��B�@�@�@��������ɘA��Ă����B�O��y�̊X�̒����Ԃ����ł����͕̂���������߂Ă̌o���B�Ԃ����������Ă����Ɠ��H�̃f�R�{�R��i���A����≺���ȂǁA���i�����Ă���Ƃ��͋C�Â��Ȃ����̂������Ă��Ċ��S�[�����Ƃł����B
�u�~�l���o�̞��͗[���ɔ�ԁv�̏o�T��T���i��C�M���u�����Ȓ��ɂāv�j�@�F�@ �@���̒��́u�����[�v�Ƃ������M�̒��ɁA��C�����w2�C3�N�̍��i1950�N����j�f������L�̌��t�̏o�T��m�肽�����āu�����͂����玖�T�ނ��Ђ�����Ԃ��A�}���قɏo�����ĕ��������Ă����v�Ƃ̈ꕶ���������B���ǁA�Ȃ��Ȃ�������Ȃ������Ƃ̂��ƁB�@�@�@���Ȃ�C���^�[�l�b�g���J���E�B�L�y�f�B�A�i�ԈႢ���܂܂�Ă���Ƃ̎w�E���������j�Ȃǂł����Ƀw�[�Q���́u�@�N�w�v���炾�ƒm��邵�A���̊܈ӂ́u�l�i�N�w�ҁj�����̎���𗝉��ł���̂͂��ׂĂ̎��ۂ��o�s�����Ă��炾�v���Ƒ�܂��ɂ͂킩�邪�A�����͑��ŒT�����̂��ȂƊ��S�[���B�@�@�@�u�푈�Ɖƒ�̎���ŁA�A�J�f�~�b�N�ȋ������@����킵���f���́A��w���o�����N��̗F�l���m���~�������������悤�ȋC������B�Ɗw�Őg�ɂ����p��͉p���Ȃ��o���F�l�ɗD��Ƃ����Ȃ������v�@�@�@���̎�����A���Ԃ݂��A��w�Ȃǂɍs���s���Ȃ��ɍS��炸�m���~��w�ё�����ӗ~�͑���ȂƍĊm�F�������B�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�i�X�A�g�}�g�̎�d���i�|�b�g�j�B�L���M���\�E�̎�܂��i���j�B�u���̔��v�̉Ԏ��͂̑����
���@�F �@ �ʐ^�̉E�̐��͂܂������엿����炸�A���͂���ɒǔ�̂ݎ{�������́A���͎�d���̎��ɔ엿�܂���͔̑���{�������́B�E�ƍ��ł�15�p��30�p�A�������{�قLj���Ă��Ĕ엿�Ȃ��ł͂܂��܂��������y�̏Ȃ̂��ƍĊm�F�ł��B�@�@�@��k�N�E���엿�͔|�͊J�n�����Ȃǂ̌��ɂ߂�����B6���H�̎��n�͂ǂꂭ�炢�̍����ł��邱�Ƃ��A�S�z���y���݂ł��B �@�@�@�E�@�F �@ 2�N�O�ɕc���w�����ĐA����������ꂪ�ł����`�K���ɕ���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ��Ԃ����Ă���Ă���̂͂��肪�����B�ߓ��A����肾���ł��`�K������菜���A�����엿�����������Ƃ���ł��B



�엿�̗L���ɂ�鐬���̈Ⴂ �y�`���j�A�ƍ̉� �ԃ���
���@�F �@ �����̋��̊x��茩���낵�ĎB��B�����͖k���̊C�ӂ���B���Ă���̂ň��������ł��B �@�@�@���E�E�@�F �@ ���̎ʐ^�A�J�[�u�~���[�ɂ͐����̗[���̌��i�����̂悤�ɉf���Ă��āA�����̏�̗[�����܂Ԃ����B�U��Ԃ��Ď��ۂɐ��������Ă݂�ƉE�̎ʐ^�̂悤�ɗ[���͌����Ȃ��B�@�@�@�J�[�u�~���[�̈ʒu��������̖ڐ���菭���������Ƃ�ʖʋ��ł��邱�ƂȂǂ��W���Ă���̂ł��傤���A��u�L�c�l�ɂ܂܂ꂽ�悤�ȕs�v�c�Ȋ��������āA���낢��ƍl�������Ƃł����B



���㓇 �J�[�u�~���[�ɉf�����[��� �������A���ڂ̗[���
3��13���i���j����@�@�@�ߑO�͏����_�����������A�ߌ�͉�����ԂɁB�k���ʂ���ł͂Ȃ��쐼���牸�₩�ȕ��������A�ō��C����19.9���B�܂��ɏt�{�ԂƂ��������ł��B�@�@�m�l�̘b�ł�3��15������̖ڈ��ŁA���̓����߂���Ƃ����������Ԃ�Ԃ����Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A���d���Ă����S���Ƃ̂��ƁB��܂����x��C���Ȃ̂ŋ}�����Ǝv���܂��B
�E�O�C�X�͉ߏd�J���H�@�F�@ �@�E�O�C�X���t�{�ԂƂȂ����̂����ꂵ���̂��A�{����6�F20������n�߂��B�܂����̏o15���O�Ȃ̂ɁB�����ē��̓�15����̌ߌ�6�F40����܂Ŗ������Ă����̂ŁA�s��12���ԋ��̘J���ł���B������قړ��l�������̂ł��炭�͂��̏�Ԃ������̂ł��傤�B����A���ꂩ��}���ɗz�͒����Ȃ��Ă����̂ŁA�������Ƃ���5�F30���炢����19�F00�܂�16���Ԗ�������̂��낤���B�@�@�@������Ƃ��Ă͐����Ȃ����Ƃ��ł���̂ł��ꂵ������Ȃ̂ł����A�{�l�H�͑�ς��ȂƎv���܂��B�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�W���K�C�����n�B�u���̔��v�̉Ԏ��͂̑����Ɣ엿���
���E���@�F �@ 11���ɐA�������́B1��2���̊����ŗt���ɂ�ł��܂����������傫���Ȃ肫��Ă��Ȃ����̂������B10�~�ʑ�A1�~�ʑ�̂��̂��O���̈�قǂ��߂Ă��܂��B������V���Ⴊ�ɕς��͂Ȃ��B�悭����Č{�ƈꏏ�Ɏύ��݁A�W���K�C���X�[�v�H�ɂ��Ē����܂����B�@�@�@�u��D���v�̑Ό�Łu��s���v�Ƃ������t�������сA���̗���Łu��s��v�Ƃ������t�͂����Ȃ���Ǝv�����ׂĂ݂��B�u�V�����@���ꎫ�T�v�i2006�N�Łj�ɂ́u��s���v�u��s��v�Ƃ��Ȃ��B�������A�C���^�[�l�b�g�����Œ��ׂ�Ƒo���Ƃ�100�����ȏ�̃q�b�g������B�V�������t�Ƃ��Ē蒅���n�߂Ă���̂��ȂƎv�����B �@�@�@�E�@�F �@ �W���K�C���̓P�c���C�V�i�G�r�X�O�T�j�Ȃǂ̗Δ����Ă����ƁA�s�k�N�ő哤����āA���̌�Ɏ�C����A�����B���n���[�߂Ɍ@���Ă݂�ƒn���ɂ͂܂�����ȑ������������Đ����Ă���B2�N�ԉ���o���@��Ȃ������̂ɂ��炢���̂ł��B



�W���K�C�����n�P�@�@�@�Q���� �W���K�C�����n�Q�@�@�@��s��H �W���K�C�����n�R�@�@�@�܂�����ȍ���
�S�@�F �@ �����̑�r��̊C�����]�A���₩�ȊC�Ƌ�ɗΔZ���Ȃ����n�}�E�h�������ΏƂł��B



�C�̑�1�@�@�@����� �C�̑�2�@�@�@������ �C�̑�3�@�@�@�k����
3��14���i�y�j����@�@�@���₩�ȉ����B�������A�ߌ�x���͉_�͂Ȃ��̂ɂ������������������悤�ɂ�����Ă��āA�����̉J�̗\��͓�����̂悤�ł��B
���R�̏o��Łi�f��@�uTATTOO���h������v�j�@�F�@ �@����́u�c��X�^�C���@�ȂƂ��ĕ�Ƃ��ā@���D�E�������q�v�ł́A�җ���}����ޏ�������܂ł̕��݂�U��Ԃ��Ă����B�k�C���̔_��Ő��܂��������o�c�ɍs���l��Ƒ��S���œ����ɈڏZ�B1970�N�A15�̂Ƃ��A���Z���̔D�P��k�[�h�p�Ƃ������ʼnf��E�Ƀf�r���[���Ęb��ƂȂ肻�̌���������������A1977�N���D�ƂɃX�g���X�������Ď��E�����A���̌�����䂩��̎��H�Ȃǂ̎������������Ƃ̂��ƁB1982�N�A�uTATTOO���h������v�ɏo���������A���̊ē̍������Əo����������B���݂͏��D�Ƃ������Ȃ����⑷���܂�4����9�l�ŕ�炷�ƒ�ł͎�w�Ƃ���1��4��̎����������ȂǕ������Ă���Ƃ̂��ƁB�@�@�@�ޏ��̏o����i��1�{�������Ă��Ȃ��B�uTATTOO���h������v�����������c�n��́u����c���|�v�ŁB����30�N�ȏ�O�Ȃ̂ŋL���͂����܂������A�F�藳���������O�Ɖ��O�̉�̂悤�Ȓj�ɓ����͂��Ă������X�ɔ��������ނ悤�ɂȂ��Ă����A�e�̐[�������������ɉ����Ă���Ɗ������B�@�@�@�Ƃ�����A���̉f��ւ̏o�������R�A���̉��₩�Ȑ����̋N�_�ƂȂ����悤�ŁA���ꂵ�����Ƃł��B�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@���r���O�X�g���E�f�[�W�[�̈ڐA�B�T�c�}�C���E��C���̕�������
�S�@�F �@ �m�l��Ŗ������Ă��邱�̉Ԃ�7�C80���قǒ����ĉ䂪�Ƃ̉Ԕ��ɈڐA���܂����B�@�@�@��N��U��Ԃ��Ă݂��3��20������ɂ͂������J�ł�������A���N�͊������������Ԃ̊J�Ԃ��x��Ă��邩���킩��܂��B����ɂ��Ă����͏��̂��Ƃ��H�N�₩���ł��B



�m�l��̃��r���O�X�g���E�f�[�W�[1�@�@�@�{�� �m�l��̃��r���O�X�g���E�f�[�W�[2�@�@�@��N3�� �m�l��̃��r���O�X�g���E�f�[�W�[3�@�@�@��N3��
�S�@�F �@ 3�������̉��₩�ȊC�B�@�@�@��n���͂ސΊ_�͏�̂悤�Ɍ��ł��ȂƊ����܂��B������R���N���[�g���ɕς����Ƃ�����A�Ί_�������ꂽ�܂܂̂��̂�����܂��B�������\�N�ԕ�Q��ɗ���l���Ȃ��悤���̕�͗҂������̂�����܂��B



��n�e��萼��]�� ��n���͂ސΊ_�ƍ��㓇 �}���A���ƍ��㓇
3��15���i���j���J�̂�����@�@�@�\��ł͉J�̂��܂�ŁA��������z�͔q�߂Ȃ��Ǝv���Ă����̂ɌߑO�̑����������琰��Ă��ď��Ă��v�킹��z�C�ɁB�ō��C����21.2���ŁA�앨�͍��̉J�ɉ����Ă��̏����ŃE�L�E�L���Ɗ����܂��B
�ق�Ƃ��̕����Ƃ́i�u���C����10�N�v�j�@�F�@ �@�@����́u�����̓��� �`�������������n�k ���C����10�N�`�v�Ƃ����ԑg�ł́A10�N�O�̕������������n�k�ʼn�œI�Ȕ�Q�������C���̂��̌�ƌ������ނ��Ă����B�Z��Č������߂�Z���ɑ��A�����s�͏W���̓y�n���ׂĂ��s�ƍ��̗\�Z�Ŕ����グ�A��U�X�n�ɂ��������ŏW���Z���ˌ��ďZ������݂���̂���ԑ����ł���Ɠ`�����B���̂��߂ɂ͂��ׂĂ̏Z������c��X�̓y�n��������Ƃ�����a�̌��f���K�v���������A���ӂ����藧���A2�N��ɂ͏W���Z��A���N�ɂ͌ˌ��ďZ����������B�@�@�@�������āu�����̃��f���v�Ƃ܂Ō���ꂽ���̓������A����͒n�k�Ȍ�t���������������Ɠ������l��6��������A��l��炵�������A�ǓƎ�������Ƃ̂��ƁB���̎����������82�̒j���́u�n�k���N���Ă���l���ς���Ă��������Ă���܂�����ˁv�ƌ���Ă����B�ȑO�͓��S�̂��Ƒ��̂悤�ŕt���������p�ɂ��������A�W���̓��͐l������Ⴆ�Ȃ��قNj������������ŏo��Ɨ����~�܂��Ă����ܘb�ɉԂ��炢�Ă����B������͓����L���Ȃ藧���b�����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A�m�l��K�˂�ɂ��`���C���������ăh�A���J���˂����Ȃ��̂ŋC�y�ɍs���Ȃ��B�s��ł����Ȃ����Ƃ��Ǝv���Ă������A���A�ׂ��������Ă���l���m��Ȃ��A�Ƃ̂��ƁB�@�@�@�Z���݂�Ȃ��C��������ɂ��ďZ��ȂǍČ��𐬂������Ă��A����͂����Ȃ̂��Ǝv�����B�^�̕����Ƃ́H�ƍl��������ꂽ�B�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�L���E���A�E���A�������̎�܂��i�Z���j�B�J�{�`���̎�d���i�|�b�g�j�B�j���W���̎�d���i���d���j�B�n�N�T�C�A�J���t�����[�̒�A�B
���E���@�F �@ 1�����قǑO�̒�A���ɂ͊����20�p�قǂ͑��������ēy�݂̂������̂��A���̊Ԃɂ�����Ȃɑ��Ɉ͂܂�ĉԂ������Ȃ��قǂɁB����͑���肷�邵���Ȃ��A�ł��B �@�@�@�E�@�F �@ �j���W���A�^�}�l�M�A�G�m�L���A���R���j���N�A�ؓ����u�ߎςƂ��������B�@�@�@��ŏ��������C���̎�����͎q�ǂ��ɐ��b�������܂���80���߂��Ă����l��炵���n�߂��B�u�j�q�~�[�ɓ��炸�v�ň�������ゾ�Ƃ̂��Ƃŗ����̌o���͂܂������Ȃ��B���̔ނ����ȗ������ǂƗ������Ă����̂����āA�䂪�Ƃɂ������悤�ȍޗ����������̂ō���Ă݂��B����C���Q��������Η������Ă����Ƃ����F�����ɂȂ����̂����A�܂��Ԃ̒i�K�Ŏ��n�܂ł�2�T�Ԃقǂ����肻���ł��B�@�@�@���͂܂��܂ł����B



�T�N���\�E1�@�@�@�����O �T�N���\�E2�@�@�@������ ��������
�S�@�F �@ ����̎ʐ^�B�ߑO�͐���ĊC�̑������ꂢ�ɉf���Ă������A�ߌ�͂����n�߁A���]�������Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂����B�����Ė�͂܂Ƃ܂����J�ƁA�{���͔��ʼn������悤�ȓV��̕ω��ł����B



��n���͂ސΊ_�ƊC�i�ߑO�j �J���R���I�ƊC �I�m�g�b���ƊC�i�ߌ�j
3��16���i���j�����@�@�@���������_���������������ɏ����A������_�̂Ȃ����ɁB�����قƂ�ǂȂ��ŁA�_��Ƃ����Ă���Ɗ����ǂ��Əo�Ă��܂��B
�����炩�Ȏ���i�u�}�b�T���v�́u�����S�̉S�v���āj�@�F�@ �@�@��T�̘A���e���r�����u�}�b�T���v�͐푈����̏�ʂŁA���x���u�����S�̉S�v������Ă����B���̎�����ے����閼�Ȃ��Ɗ�����B�@�@�@���̋Ȃ̈�Ԃ̎v���o�́A�w������̃[�~���h�ŎЉ�l�Ƃ��ē����Ă���[�~��y����������ɗ��Ă���A�]���ʼn̂��Ă��ꂽ���ƁB�u�����N�w�v�Ƃ����d���[�~�̐�y�䂦�A�ǂ�ȍ����ȉ����܂��͉̂��I���Ă���邩�Ǝv������A�Z�N�V�[�ɍ���U��v���X���[���̂��A���u�����S�̃��̎����H�ɕς��āE�E�E�A�����A�݂�Ȃʼn̂��܂��傤�v�Ɗ��Ԃ�߂�悤�ȃ��C�̂��̂��n�߂��̂Ŗڂ��ۂ������B�@�@�@���������A���w����w�N�̎��A��y�̎w����10�l�O�オ4�C5���̍����̐Ί_����C�ɔ�э��܂���A���̐܁A���C�̐����̂���Â̂킳��Ă͋ɖ��o���̂��v���o���B�u1�f�@�C�����m�P���`�����g�@�@2�f�@�j�N���m�n�i�`�����g�@�@3�f�@�T���}�^�q�b�J�k�C�f 4�f�@�V�b�J���_�L�A�b�e�E�E�E�v�@�������͂��ꂢ�Ɏl�ܒ��œ��ꂳ��Ă��Č����ł��B���������N��������̂��낤�B�@���ł��̎��͑N���Ɋo���Ă��Ďq�ǂ��̎��̋L���͖Y��Ȃ����Ɗ��S����B���₢��̂������A���ʼn̂������͑z���ɂ��C������B�@�@�@���̗ǂ������͓�����A����Ȃ����炩���̂����ŏՓ����O�������Ă�Ȃ������̂����Ƃ��v���B���͂ǂ��Ȃ̂��낤���H�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@���ݍ��݉������B�C���W�߁B�X�C�[�g�s�[�̒�A�A�[���j�E���̈ڐA�B
���@�F �@ ��N�H�ɐΊ_��y��ɕς��A�y�݂̂������̂����X�ɑ��������Ă��Ă��܂��B�@�@�@�y���ɂ�������⍪������o���Ă���̂ł��傤�B����ɂ��Ă���ނ̑����ɋ����܂��B �@�@�@�E�@�F �@ �Ԉ��������_�C�R����20�p���炢�ł����B������������ƒ����A���ꂪ�����Ă��Ă��̃_�C�R���ɂȂ�̂��Ɗ��S���܂��B�@�@�@�c�}�~�͏�����݂������Ă��������̂ɁA��͎c�O�Ȃ�����B�Ԃ��炫�����̂��̂̓R�b�v�ԕr�ɓ���Ϗܗp�Ƃ��Ċy����ł��܂����B



�ԃ��� �z��������̓y�� �Ԉ����_�C�R���ƃc�}�~��
�S�@�F �@ ����̎ʐ^�B���キ�A�z�˂������������Ȃ��A�����������₩�ŐÂ��ȊC�Ƃ�������ł��B



���₩�ȊC1�@�@�@�k���� ���₩�ȊC2�@�@�@������ ����C�ƃ}���A��
3��17���i�j�����̂��܂�@�@�@�_��Ȃ���͗l�̒��A�ߑO������C�����}�㏸�����O��26�x���ĉē��ƂȂ�B���Ǎō��C����27.2���ƂȂ�A��C��5���̗z�C�Ƃ��������ł����B�������ߌォ�炷���ɓ܂�n�߁A��ɂ͑�J�ƂȂ��Ėڂ܂��邵�����ł����B�@�@�@��̓��ꎕ�̋���������Ȃ̂Ŏ���҂ɍs���B�㉺�Ƃ������ꎕ�ŁA���H��͂����Đ̂���`���Ă��܂����A�������������ꎕ�ɂȂ鎞��������̂��ȂƊ��S�[�����Ƃł��B
�u�w�ς��ʈ��x�͂��邩�v�i�I�����@�u�Y�ޗ́v�j�@�F�@ �@�@�������҂ɘA��čs�����Ƃ��A�ҍ����ɂ��̖{���������̂ł�����ƊJ���Ă݂��i2008�N���j�B�@�@�@�@�Ėڟ��Ƃl�D�E�F�[�o�[�̒����������f�ނɂ��āu���̂��߂Ɂw�����x�̂��v�A�u�Ȃ�����ł͂����Ȃ����v�Ȃǂ̏͗��Ăōl�@���Ă����B�@�@�@���̒��Ɂu�w�ς��ʈ��x�͂��邩�v�Ƃ����͂��������B�ނɂ��u���Ƃ́A���̂Ƃ��ǂ��̑��݂̖₢�����ɉ����Ă������Ƃ���ӗ~�̂��Ɓv���Ƃ̂��ƁB������ߒ��ł͏����̏u�ԓI�ȐⒸ�𖡂키���Ƃ����낤���A���퉻�������Ă��܂��āu���Y�n�v�Ɗ����邱�Ƃ����낤�B�������A���̖{���͖₢�A�����邱�Ƃ̘A�����ƍl���Ă���悤�ł���B�@�@�@�����w�҂Ƃ��Ă̔ނ����m��Ȃ��������A�D�~���[���ȂƊ��S�����B�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�g�E�����R�V�̎�d���i�Z���d���j�B���l�M�A���^�X�A�T���_�̎�d���i���d���j�B�S�[���[�̎�d���i�|�b�g�d���j�B�r�j�[���g���l���̊J�B
���E���@�F �@ ����12���Ƀ}���`�����ĐA���A���낻����n�����߂��̂ɁA�u���̔��v�̕��͂܂��肪�o������̗l���ł��B�o���Ƃ��엿�͂�炸��C���̏�ɕ~��������u���A���̏ォ��y��킹�����́B�u���̔��v���̓��b�J�Z�C�̌��Ȃ̂ŗ{�����c���Ă����̂ł��傤���A����Ȃ�u���̔��v���͓����}���Ȃ̑哤�̌��Ȃ̂œ��������ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����B�@�@�@��l������̂́A�u���̔��v���̐��͔��y�������Ă��Ȃ��`�K�����������y��킹���̂ŁA���ꂪ���y����ߒ��œy���̒��f�������������������Ȃ��Ƃ����ƁB���n�ȗL�@����y���ɓ����ƍ앨�̏o���������Ƃ����m�l�̌��t��g�������Ēm������������܂��B �@�@�@�E�@�F �@ �Z��ł������͍�N���ɓs��Ɉڂ�Z�̂ō��͎�̂��Ȃ��ƁE���ł��B�������A���ڂ�킩�甭�肵���̂��A�݂��Ƃȃ_�C�R�����炿�A�������Ȃǂ̍̉Ԃ����J�ł��B�݂��ƂȂ����ɁA�t�ɗ҂������̂�܂��B



12���A���W���K�C��1�@�@�@�u���̔��v�� 12���A���W���K�C��2�@�@�@�u���̔��v�� �傪���Ȃ��Ȃ�����
�S�@�F �@ �����ő��������C���ߌ�x���ɂ͉��F�ɂȂ�B�������A���₩���͕ς�炸�B�@�@�@��́u�����[�A�Ă���ˁ[�B�܂��Ŕg��Ȃ������A�悩�ˁ[�v�Ƃ��@���ł����B



�̂悤�ȊC1�@�@�@���̂͂����萼���� �̂悤�ȊC2�@�@�@�k���� �̂悤�ȊC3�@�@�@�D�ƃI�m�g�b��
3��18���i���j�\���J�@�@�@��邩��̉J�͖钆�ɂ͂߂��炵���قǂ̑傫���ƒ����̗����Č������Ȃ�B�������������\���J�ŁA������J���Ƃ��ɋ����B�@�@�@�Q�Ăč��H�𒅂āA�x��ɒx��Ă����\���}���x���𗧂Ă����Ƃł����B�����J�ɓ��Ă悤�ƊJ���Ă����W���K�C���g���l�����A�s���|�ꂽ�萁�����ł͌����q���Ȃ��̂ŕ߂܂����B
�u���̂��߂Ɂw�����x�̂��v�i�I�����@�u�Y�ޗ́v�j�@�F�@ �@�@����̑����B��̃^�C�g���̏͂Łu�l�͂Ȃ������˂Ȃ�Ȃ����v�Ƃ̖₢�ɑ��A�ނ͎Љ�I�ȑ��҂��珳�F�̂܂Ȃ����i�A�e���V�����j�邽�߂ł͂Ȃ����ƌ����B�����āA���݂͂�����d�����T�[�r�X�Ɖ����Đl�ԊW�����C���Ƃ���R�~���j�P�[�V�����E���[�N�X���K�v�Ƃ����X��������B����̓P�[�X�o�C�P�[�X�ł��邽�߁A�܂��u�P���J���ƈ���ă}�j���A�������ɂ������߁A���̂��̂̍H�v�Ɠw�͂Ŋ撣��˂Ȃ炸�A���̂��_�o���t���Ɏg�����ƂɂȂ��āA�S�g�Ƃ��ɔ��ĉʂĂĂ��܂��܂��v�Ƃ��q�ׂ�B�T�[�r�X�Ƃ́u�ǂ��܂Łv�Ƃ����������Ȃ����߁A�T�[�r�X�c�Ƃ�ߘJ���ȂǂɂȂ���댯������B����܂��������ŁA�ɂ�������炸�A�ނ͂����ɂ͐�剻���ꂽ�������E�Ƃ��́u�S�l�i���v�����߂��\�����傫���̂ł͌����A���̏͂���߂������Ă���B�@�@�@�����Ӗ��́u�������v�u�Љ�ɎQ������v�u���Ȏ�������v�̎O���Ƃ͂悭�����A�ނ�����P���Ă���Ɗ�����B�{���̃j���[�X�ł͍��N�̏t���̐��ʂƂ��đ啝�ȃx�[�X�A�b�v���ڔ������Ƃ����b�肪�傫�����グ���Ă������A���[�L���O�v�A�̖��͂܂��܂��[���Ȃ悤�ŁA���̌���ɂ������C���̗͂𒍂��łق����Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�\���}���̎x�����āB�W���K�C���̃r�j�[���g���l���߁B
���@�F �@ �P�����قǑO�A�ߏ��̎ʐ^�B1�w�N�^�[���قǂ̍L���ɗc�c�����R�ƐA���t�����Ă��đs�ςł��B�������ɂ͎��n�ԋ߂̔�������A���̍앨�͂��������ɂȂ��Ă���̂��ȂƊ����܂����B�����ł�����ꂵ�����Ƃł��B �@�@�@���@�F �@ ��ʂ��Ă����`�K���������Ă��܂��B�V�C�W�O�Z���`���[�g���Ɉ���Ă���A�~�������ɍœK���Ɗ����܂��B�����͔͐̂��ŁA�T�c�}�C���┞������Ă����̂��Ǝv���܂��B�`�K���ł���Ă��Ǘ����s���͂��Ă���̂́A�r��đ�ɂ������Ă���̂��͂��ꂵ���B�@�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ �������͔̂��������B�|�ɂ������Ă��܂��҂�������ł��B�@�@�@



�u���b�R���[�� �`�K���i���j���H �r�ꂽ��
�S�@�F �@ �����̎ʐ^�B�@�@�@���̓y��ɒ|����{��{����Ȃ���~���l�߂Ă����ƃJ���R���i�����X���C�X�����T�c�}�C���j�������I�ƂȂ�܂��B�������\�N�Ԓ|���~����邱�Ƃ͂Ȃ����u����Ă��܂����A�܂������ē|�ꂸ�������Ɨ����Ă��Č��C�ł��B�C���₵�Ԃ��̂̂����ŕ���ɂ����̂�������܂���B �@�@�@



�J���R���I�y��ƊC�̑�1 �J���R���I�y��ƊC�̑�2 �J���R���I�y��ƊC�̑�3
3��19���i�j�J�̂��܂�@�@�@�J�͖�36���Ԃ����ƍ~�葱���ŁA���O�ɂ�ށB���̎��͂�Ԃɂ͐������܂����ӏ��������A���͂��̂����Ƃ��눫���Ƃ��낪��ڗđR�ł��B���y�M��60�����L�[�v���Ă������ݍ��݉������Ȃ�Ɛ������܂��Ă��Ĉ�C��20���ɉ�����܂����B����͂�A���R�ɂ͏��Ă܂���B�@�@�@��̒܂���`��������B����͎����Ń`�������W���邪�A�E�藼���͂��������ɂȂ��Ă����B�̗͂������Ă��܂┯�͕ς�炸�L�тĂ����̂͂��ꂵ�����Ƃł��B��������R���B
�u�Ȃ�����ł͂����Ȃ����v�i�I�����@�u�Y�ޗ́v�j�@�F�@ �@�@�܂�����̑����ł��B�@�@�@���̃^�C�g���̏͂ł́A�ŋ߂̂����܂��������ʎE�l�����⎩�E�̑����́u�l�̖����y���Ȃ��Ă���v�悤�ł����犦���v��������ƛI���͏q�ׂ�B�Ȃ�����̈Ӗ����y���Ȃ��Ă��܂����̂��B�g���X�g�C�́u�����ɐi�����Ă��������̒��ŁA�l�̎��͖��Ӗ��ł���B�������Ӗ��ł���ȏ�A�����܂����Ӗ��ł���v�Ƃ̌��t�����p���A�u�l�����R�̐ۗ��ɑ�������炵�����Ă���Ƃ��́A�L�@�I�ȗ։�̂悤�Ȃ��̂̒��ŁA�����邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ��قڊw��ŁA�l���ɖ������Ď��ʂ��Ƃ��ł��܂��B�������A�₦�ԂȂ����W�̓r��ɐ����Ă���l�́A���̎��ɂ������l�������Ȃ��ꎞ�I�Ȃ��̂����w�ׂ��A�����Ė������邱�ƂȂ����ʂ��ƂɂȂ�܂��B������A�m������̂̓����Ȃ����͈Ӗ��̂Ȃ������̏o�����ł���A���Ӗ��Ȏ������^���Ȃ������܂����Ӗ��ł���v�Ƃ̈ӂ��낤�Ɖ��߂���B�@�@�@�Ėڟ��́u���R�ƓƗ��ƌȂ�Ƃɏ[��������ɐ��܂ꂽ��X�́A���]���Ƃ��Ă݂�ȍ��҂��݂𖡂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�v�i�u�S�v���j�Ƃ������t�̂��Ƃ��A����̐l�͋����̂�`���I�����������������Ď��R�ɂȂ������ʁA�ǓƊ��ɂ����Ȃ܂�u���ׂ̂Ȃ��v�ɋꂵ��ł���B���̂��߂Ɏ��\�����ɂȂ�����A�u���R����̓����v�i�d�E�t�����j�̂��Ƃ��V���@�����܂ށu�X�s���`���A���v�Ɉ��S�����߂���l�X�ȑΉ����݂���B����ȏ̒��Łu������́v��ɂ͂ǂ�����悢�̂��B�@�@�@����́u���̂��߂Ɂw�����x�̂��v�ŏq�ׂ��̂Ɠ������A�I���́u���҂Ƃ̂Ȃ���v�u���ݏ��F�v��ڎw�����Ƃ��J�M�ł͂Ȃ����ƌ����B�u�w�l�Ƃ̂Ȃ�������l���Ăق����v�Ƃ͌��������̂ł��B�Ȃ��邽�߂ɂ͂ǂ������炢�����l���āA���̈Ӗ����m�M�ł����Ƃ��A���Ԃ�A�w���x���w���x�������A�����ɏd�݂����߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�����M�������̂ł��B�@�@�@���������Y�݂܂����B�i�����j�@�@�@���҂����F���邱�Ƃ́A�������Ȃ��邱�Ƃł͂���܂���B��������������F���āA����������ɏ��F�����B���������������͂ŁA���͎��Ƃ��Đ����Ă�����悤�ɂȂ����Ǝv���܂��B�������ł��邱�Ƃ̈Ӗ����m�M�ł����Ǝv���܂��B�@�@�@�i�����j������Y�ނ��Ƒ傢�ɂ��������Ŋm�M�ł���܂ő傢�ɔY�炢���̂ł��B�@�@�@���r���[�ɂ��Ȃ��ŁA�܂��߂ɔY�݂ʂ��B�����ɁA���̐l�Ȃ�̉��炩�̉�����Ǝ��͐M���Ă��܂��B�v�@�@�@���̖{�̑тɂ́u�s���Ɛ�]�̎�����������߂́w�^�̗́x��b���グ�����@�@�@75�����˔j�v�Ə�����Ă����B�ݓ�2���Ƃ��Ă��̍����₱�̐��ɂ������ꏊ���Ȃ��Ɗ����ĔY��A�u���v��ԂɂȂ������Ƃ����钘�҂̌o���������A�[���͋������e���킩��₷�����́E���t�ŏq�ׂ��Ă��āA�֑�L���ł͂Ȃ��ȂƊ������B�@�@�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�u�Ƃ̑O�̔��v�Ɓu���̔��v�̉ԊԂ̑����B�`�K���̐�Ԃ��B
�S�@�F �@ �ǂ̎ʐ^�ɂ����J�̍̉Ԃ�������Ă��āA�₩�����������ĂĂ��܂��B����̖\���J�œ|�ꂽ���̂������A����̃T�������n�߂������o�Ă��Ă���̂ŁA�̉Ԃ̎��������낻��I���ł��B



������̉Ԕ�1�@�@�@�`���[���b�v�A�y�`���j�A�Ȃ� ������̉Ԕ�2�@�@�@�p���W�[�Ȃ� ������̉Ԕ�3�@�@�@�i�f�V�R�A�X�g�b�N�Ȃ�
�S�@�F �@ �����̎ʐ^�B�@�@�@�{���̎U�����͉J�オ��̓܂��ŁA���̎ʐ^���͏����g�������Ă��܂����B �@�@�@



�D�ƃ}���A�� �D�ƃI�m�g�b�� ����@�ƕP��
3��20���i���j�܂�Ƃ��ǂ�����@�@�@������܂�̗\�������A���O���琰��Ԃ������Ă����̂ōQ�ĂĐ��������B3���Ԃ�̐���Ԃł��ꂵ������B�@�@�@11��̉Ԃ̎��d���B�݂ȉ肪�o�Ĉ������A�ԉ����ł������ł��B
�u�č��E�H�ォ��v�i�u�r�b�O�C�V���[�@���{�Łv���j�@�F�@ �@�@2���A����w�O�̘H��ōw���������́B�u�z�[�����X�̎d�������莩������������v�G���Ƃ̂��ƁB�@�@�@2��15�����iVol�@257�j�ɏ�̃^�C�g���̋L�����������B���܃A�����J�ł�40�N�O�ɏI������͂��̃x�g�i���푈����̋A�ҕ����͂��߁A�u�C���N��A�t�K�j�X�^�����܂ސ�ꂩ��̋A�ҕ��z�[�����X���ő�40���l�ɏ��A�z�[�����X�l����40���ɒB����Ƃ̐��v������v�@�u�Đ��{�͂���Əd�������グ�A�A�ҕ��̘H�㐶���҂����炷����ɗ͂����A���̐��͌������v�Ƃ̂��Ƃ����A����ł��z�[�����X������Ȃɑ����̂��Ƌ������B�@�@�@�������ݕăW���[�i���X�g�̊�c���́u���ꂾ�������̐l���z�[�����X�ɂȂ�̂́A�l���E���d���̃g���E�}���A�l�ԊW��j�Q���A�����m�������Ǘ������邱�Ƃ���Ă���v�ƌ���ł����B�@�@�@�܂����A�{���̒���V���ɂ́u���ۖ@�ā@��^�A�x�O�Ɂv�Ƃ̋L��������A�������}�́u�W�c�I���q���s�g���\�ɂ���Ȃǎ��q�������g���}��֘A�@���̍��i�𐳎����肷��v�Ƃ̂��ƁB����p�ł͖^�}�̌��}��e�����u���@�����@���{�����v�Ɛ����r���Ă����B�@�@���ꂩ��ǂ��Ȃ��Ă����̂��A�s�����̂�܂��B�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�Ȃł����A�A�X�^�[�A�肪�ˑ��A���t�ڂ���A�C���p�`�F���X�A�R�X���X�A�L�����f�B�[�|�b�v�i����g�j�A�}���[�S�[���h�A���A�S�����A���m���c���̎�܂��B�@�@�@�`�K���̐�Ԃ��B
���@�F �@ �傫���Ȃ肷���ĉ��ɂȂ����_�C�R���Ɏ����킸�A�������ȉԂ��炩���Ă��܂��B �@�@�@�E�@�F �@ ��N�t�ɓ��삩�玝���Ă��ĐA�����c�o�L�B���t���ĉԂ��炩���Ă��ꂵ�����Ƃł��B



�I�X�e�I�X�y���}���ƍ̉� �_�C�R���̉Ԃƍ̉� �c�o�L
�S�@�F �@ �ɂ��āi������āj���Đ��������킩��Ȃ��قǂł��B�z�͉_�̂����Ԃ��班����������x�ł������A���͎キ�����U�����a�ł��B �@�@�@



�ɂ�C1�@�@�@�k��]�� �ɂ�C2�@�@�@����]�� �ɂ�C3�@�@�@���]��
3��21���i�y�j�܂�̂������@�@�@�܂�̂�����Ōߌォ�琰��̗\�������ߑO�̑���������������ƂȂ�B�ō��C��26.6���̉ē��B�������A�C���ɂ��Ă���͍̂�����l�ŁA���̂��������D�͏��Ȃ߂ł����B
�z�g�g�M�X�̓E�O�C�X�̋N�������H�@�F�@ �@�@�E�O�C�X�����n�߂鎞�Ԃ�13����6�F20�������̂��A�����6�F15�A�{����6�F10�Ə��X�ɑ����Ȃ��Ă���B���̏o���������܂�ɂ�A����10���ȏ�O�ł�����C�̕ω��������Ă���̂ł��傤�B�������\�͂��Ǝv���܂��B�@�@�@�@�ʔ����̂͂���3���ԂƂ��������������A�قږ����̂悤�ɃE�O�C�X�̂�������5���O�Ƀz�g�g�M�X�����n�߂邱�ƁB�{����6�F05�Ɂu�M���b�M���@�M���M���M���I�v�̖������������A����5�����6�F10�Ɂu�z�[�@�z�P�L���v���������n�߂��̂������B�@�@�@�l���悤�ɂ���ẮA�z�g�g�M�X�̓E�O�C�X���N�������A�������͖��n�߂�̂𑣂��������Ă���̂�������Ȃ��Ǝv�����B�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�u���̔��v�Ɓu���̔��v�̃^�}�l�M�̑����B�_�C�R���Ƒ�Y�S�{�E�̎�d��
�S�@�F �@ 3���Ƃ��ߑO10������̖������̂悤���B����3���͓����ӏ��̌ߌ�5������A�����ɂȂ����悤���ł��B



�����̊C1�@�@�@�k��]�� �����̊C2�@�@�@����]�� �����̊C3�@�@�@�쐼��]��
�S�@�F �@ �g�����₩�Ȃ̂Ŗ������ɉB��Ă����₪�������ɂ͎p�������̂��͂�����킩��܂��B����ɂ��Ă��A�����Ȃ̂ɐ������������Ȃ��قǂ��ɂŎc�O�Ȃ��Ƃł��B �@�@�@



�����̊C1�@�@�@�k��]�� �����̊C2�@�@�@����]�� �����̊C3�@�@�@�쐼��]��
3��22���i���j�����H�@�@�@�_�͂Ȃ��̂ʼn����ƌ��������̂ł����A��������ʂɔ��ł��Ă���悤�ʼn������������悤�Ȉ���ł����B�C�߂Ă������͌�����P���A���㓇�͂قƂ�nj������B�@�@�@��́u���g���Ă��ꂩ�ˁ[�B�@�@�@�����͕P������[�B�ǂ��i�ǂ��ցj�����Ă���������납���H�v�Ƃ߂��炵���Ђ傤����������Ă��܂����B
20�����A24�l�̃N���X�i�f��@�u�o�x���̊w�Z�v�j�@�F�@ �@�@�����������u�r�b�O�C�V���[���{�Łv2��15�����iVOL�@257�j�ɂ��̉f�悪�Љ��Ă����B�@�@�@�t�����X�ɂ͊O�����痈������̈ږ��̎q�ǂ�������Ώۂɂ����u�K���N���X�v��840�Z����B���̉f��̓p���ɂ��邻�̂����̈�̃h�L�������^���[�ŁA�A�C�������h�A�Z�l�K���A�u���W���A�����b�R�A�����A���[�}�j�A�A�Z���r�A�A�x�l�Y�G���Ȃ�20��������W�܂���24�l�̐��k���Ƃ��Ɋ�����ׂĂ���B�@�@�@�x���g�D�`�F���ḗu�����Ɏ���܂ő����̌o���������蔲���A�قȂ镶���I�w�i��w�����Ă��邯��ǂ��A�V�V�n�ɂȂ��݂����Ƃ������ʂ̃S�[����ǂ��Ă���B�ނ�̂��Ƃ������ƒm�肽���A�Ǝv������ł��v�u�q�ǂ����オ���������I���10��ɁA�ނ�͂Ȃɂ��v���̂��B�̋��ɒu���Ă������́A�w�����ĕ����E�@����v���o�A�t�����X�ɕ�����]�ƌ��łɂ��ĕ����Č����������B�����Ă����ɂ��Ď������g���m�����Đ����Ă����̂��Ƃ������Ƃ��f��ɏĂ������������̂ł��v�A�Əq�ׂĂ����B�݂��̍��ʂ△�m�����邯��ǁA���Ԃ������đΘb��_�����d�˂Ă��������Ɂu���̈Ⴂ���b�������������炵�A�L�����ނƂ������ƂɋC�Â��Ǝv����ł��v�A�u���҂ɑ��Ă��߂炢�Ȃ����e���������A�A�т���ނ�́A���ɂƂ��ăq�[���[�̂悤�ł����v�Ƃ��B�@�@�@10��Ŏ����̕������獪����������������邱�Ƃɂ��r�����͑z����₷��B�l�I�i�`�̊��������������Ă���ƌ����Ȃ�����A���̂悤�Ȋw�Z�𑽐��^�c���Ă���t�����X�ɂ��A�܂������ŕ�������q�ǂ������ɋ����������ĉf��ɏĂ������ēɂ����S�����B�܂��݂Ă��Њς������̂ł��B�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�I�N���A�G�_�}���̎�d���i�|�b�g�j�B�u���̔��v�ɃT�g�C���̐A���t���B�����ɃT�g�C���̉�o��
���E���@�F �@ �q���V���X��2�T�Ԃقǒx��ă`���[���b�v���炫�n�߂܂����B�������ɋ�����A���Ă����̎�ɂ���Ă��̂悤�ɂ͂�����炭�������܂��Ă���̂��Ɗ��S���܂��B �@�@�@�E�@�F �@ �ԉ肪�o�����̂����n��1�T�ԂقǗ����ł��Ȃ��܂ܕ����Ă�������_�C�R���ƒ��p�̉ԂƂȂ��č炫�n�߂Ă��܂��܂����B����ĂāA�{���A���c�����T�g�C���ƂƂ��Ɏϕ��ɂ��ĐH�ׂ܂����B�\�z�ʂ�A�����X�������Ă��܂������A�����������������܂����B



�`���[���b�v�ƃq���V���X1 �`���[���b�v�ƃq���V���X2 �k���^�_�C�R��
�S�@�F �@ ����Ƃقړ����A���O���̎ʐ^�ł��B����ł������ς��̂��Ɗ��S���܂��B�����͂ǂ��Ȃ邩�B �@�@�@



�r���C1�@�@�@�k��]�� �r���C2�@�@�@�쐼��]�� �r���C3�@�@�@����]��
3��23���i���j����@�@�@�z�͏Ƃ�̂����k���̂����������B�����A�����܂Ŋ��C�������肻���ł��B�@�@�@����͖k������̕��������̂��{���͖k�k���ɁB���̂�����Ƃ��������̕ω��ʼn����Ȃ��Ȃ�A�P���Ȃǂ͂������茩�����B��͂����̉��C��͉�����PM2.5�̂����Ȃ̂��ȂƎ����ł��B
�u�w���a�����āx�F�荞�߁v�i�Ђ߂�萶���ҁA�ŏI�u�b�v�j�@�F�@ �@�@ �{���̒���V���ɂ��̃^�C�g���̋L�����������B�u�w�Ђ߂�蕽�a�F�O�����فx��22���A�C�w���s�������Ƃ��Ă͍Ō�ƂȂ鐶���҂̍u�b���������B���i�q�ْ��i87�j�́w�푈�͐l�Ԃ��N�������̂�����~�߂���B�w�푈�͑ʖځx�ƌ�����l�ɐl�ɂȂ��āx�ƌĂъ|�����v�@�@�@�@�Ђ߂��w�k���͊Ō�v���Ƃ��ē������ꂽ����t�͊w�Z���q���ƌ�����ꍂ�����w�Z�̐��k�Ƌ��t����Ȃ�A���k��15�`19�������B�u�������n���Ɋ������܂�A240�l��136�l���S���Ȃ����B�@�@�@�����قł�1989�N�̊J�وȗ��A�����҂��c�̗̂��َ҂ɍu�b�𑱂��Ă������A�،����̌����⍂�����R�������ς��ł̏I���ƂȂ����v�Ƃ̂��ƁB�@�@�@�Ђ߂�萶���҂̍u�b�͐��k�ƂƂ��ɂS�����Ă����������B����C�w���s�ł̓r�[�`�ł̂͂��Ⴌ�܂�肪���E�y�̎��ԂƂ���u�b�q����K�}���w�͒��E�Â̎��ԂŁA���k�̐S�[���ɋ����Ă��銴���������B�@�@�@�@���b�����肪�Ƃ��������܂����B���܂ł������C�ŁB�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�W���K�C���̐A���t���i�u���̔��v2���A�u���̔��v2���j�B�T�c�}�C���̉����������ݏ���
���@�F �@ ���O�́u�}���U�N���v���Ǝv���Ă��܂������A���ׂ�ƈႤ�悤�ł��B�����Ȗł��������ɍ炫�ւ��Ă��܂��B�E�ׂ�̓X�m�[�h���b�v�ƃo���B �@�@�@���@�F �@ ���삩�玝���Ă������́B�킪�Ƃɂ͔��Ƃ��̃��C�g�u���[�̂Ɨ����炢�Ă��܂��B �@�@�@�E�@�F �@ �{���A���t�����A���f�X���b�h�ƃf�W�}�̎c��B�F������Ă��邾���łȂ��A�o���Ƃ��P���P�O���Ɏ��n�������悤�ɕۑ����Ă����̂ɉ�̏o��������Ă��Ėʔ����B�@�@�@�����������Ƃ����̂���䥂ŁA�\�[�Z�[�W�A�ʃl�M�ƍ����ăT���_�ɂ��܂����B�܂��\�����������H�ׂ��܂����B



�H �n�i�j�� �A���c��̃W���K�C��
�S�@�F �@ �{���͕P�������㓇���u�ǂ��ւ������čs�����v�A�����̏ꏊ�ɒ������Ă��܂��B �@�@�@



�����EPM2.5�̂Ȃ��C1�@�@�@�P�� �����EPM2.5�̂Ȃ��C2�@�@�@���㓇 �����EPM2.5�̂Ȃ��C3�@�@�@�}���A���ƍ��㓇
3��24���i�j����Ƃ��ǂ��܂�@�@�@�{�����~���߂��Ă����悤�Ȋ������B�v���Ԃ�ɕ�̎Ԉ֎q�������āu����@����v�܂ōs���Ă݂܂������A�����������k���������i�F���y���ނɂ͂قlj����B���X�ɋA��܂����B
�u���c�s�i�ȁv����20���N�i�u�}�b�T���v�̕��ԓm�v�v�j�@�F�@
�@�@ ����́u�}�b�T���v�ł́u�k�C���̕��v�A���ԓm�v������F�Ղ��u������������܂�����ȁB���C�łȁv�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�������Â����Ă������B�@�@�͂ɂ��悤�Ȉ������悤�ȏΊ炪��ۓI�������B�@�@�@���ԓm�v�̏o���f���1�{�����A�������ւ��r�{�́u���c�s�i�ȁv���ς����Ƃ�����B�킪�܂܂Ŕj�V�r�A�����Ĕ�Ԓ��𗎂Ƃ������̐l�C�o�D�����������͗����ڂƂȂ��Ă���B����ȁu�₿���v��̓�����Ŏ�X���������ɉ����Ă����B�@�@�@���ꂩ��20���N�A����Ȃ����Ƃ�Ƃ����V�l����������悤�ɂȂ����̂��Ɗ��S�[�������B�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�I�N���i�ۂ���A�܊p�j�A�J�{�`���i�G�r�X�A�����j�̎�܂��i�|�b�g�j�B�L���E���i�l�t�A���͔����j�̔��グ�B
���@�F �@ �I�X�e�I�X�y���}���͗z���A���Ă��炢�Ă���̂����ꂵ���B�̉Ԃ͎U��n�߂��Ƃ͂����܂��܂������ʂ��Ă���Ă��܂��B �@�@�@���E�E�@�F �@ �E�̉Ԃ����삩�玝���Ă������́B�A�C���X�ƉԂ̌`�͎��Ă��܂������O�ׂ�]�T�Ȃ��c�O�ł��B



�I�X�e�I�X�y���}���ƍ̉� �A�C���X�H �H
�S�@�F �@ ����ƊC�͂����Ǝ��Ԃ��x��������B�e�u�Ԃ��K���̂ł��傤���A�����Ă����ɑގU�ł����B



����@���P����]�� ����@����1 ����@����2
3��25���i���j�����@�@�@������A�_�͂قƂ�ǂȂ��B���͓�����k�������サ�B����䂦���A�~���߂����悤�Ȋ����ł��B����3���ԁA�ō��C���͈�����20���A�����20���A�{����21���Ƃ����ω��͂Ȃ��̂ɍŒ�C����11�A9�A5���Ɖ�����A��6���̒n�\���x��7�A5�A�}�C�i�X1���Ƃ����Ɖ���������������B�뉺�Ȃ̂ŁA�W���K�C����肪�o������̃_�C�R����S�{�E�����Ō͂�Ȃ����S�z�ł��B
���R�̉c�݂Ƃ͂����i�u�J�j5000���C�̑�s�i�v�j�@�F�@
�@�@ �����́u���C���h���C�t�@�@�I�[�X�g�����A�@�N���X�}�X���@�J�j5000���C�̑�s�i�v�Ƃ����ԑg�ł͉J�G��11���ɂȂ�Ɨ��ɏZ�ސԃK�j����ĂɊC��ڎw���l�q���Љ��� �����B�@�@�@���A���H�A���z����Ȃǂǂ�ȏ�Q�������낤�Ƃ����Ђ�����C�Ɍ������Đi�ށB9�L�����[�g���O���1�T�Ԃ����ĊC�ɂ��ǂ蒅���A�C���m�F�����炷���߂��̐X�Ɉ��� �Ԃ����ꂼ�ꂪ���������������@��B�@�@�@���͔ނ�̓I�X�ŁA3�C4���x��ē������郁�X�̂��߂ɂ��̌����@��̂������B������ʂ�������I�X�̓��X�����Ɏc���A���Ƃ��ƏZ��ł����X�ɂ܂�1�T�Ԃ����ċA��B�@�@�@�������2�T�Ԃقnjo����12�����{�A�b���Ɠ������炢�̑傫���ɂȂ������̉�i��10���j�̑܂ɕ��������X�����͈�ĂɊC�Ɍ������B�ړ�����͖̂����Ɗ����̍����ł��������Ȃ���̐[��ŁA�����Ȃ����̎���m��\�͂ɋ����B�g�ł��ۂɂЂ��߂����������X�����͂�����̂͏��ő܂�����������C�ɕ�������A�M���댯���ڂ݂��C���ɐ����ė�������M �ꎀ�ʂ��̂�����B�@�@�@���͂����ɛz���ėc���ƂȂ��ĉj���n�߁A�q�K�j�ƂȂ�����e�K�j�����̏Z�ސX��1�T�Ԃ����ĕ����B������4�N�����Đ��n������A�܂��C�Ɍ������B�@�@�@�{�\�Ƃ͂����A�ǂ�ȍ�� ���낤�ƒW�X�ƊC�Ɍ������ĕ����A���܂��������Ɉ�ĂɎq��������B�����Ă��̎q�������܂��������Ƃ��J��Ԃ������ďI��邱�Ƃ��Ȃ��B���R�̉c�݂̂���̂Ȃ��Ɉ��|���ꂽ�B�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�u���̔��v�̂���蕥���B�u���̔��v�̗Δ씰�́B
���E���@�F �@ �W���K�C���͉h���ĔZ����4�A50�p�Ɉ���Ă��܂��B�䂪�Ƃ̖��엿�̐��͔̂��ł܂�20�p�قǁB�v���Ƃ̍����v���m�炳��܂��B�@�@�@�J�{�`�����g���l���̒���4�C50�p�Ɉ���Ă��܂��B�肪�o������̂킪�Ƃ̊������ꂭ�炢�ɂȂ�̂�1�������قǐ悩���B �@�@�@�E�@�F �@ �u�Ƃ̑O�̔��v�̃j���W���A�卪��1�Ԑ��ƃJ���t�����[�A�u���b�R���[��2�Ԑ��B��N�������킪�������Ă����c�}�~����̂�����Ă������炱��Ȃɋ��剻���A�ʐ^�̐^��50�p�̐��ԂȂ̂����A���R�Ƃ����A���ʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��B



�m�l�̔�1�@�@�@�W���K�C�� �m�l�̔�2�@�@�@�J�{�`���̃g���l�� ���Ԍ�����
���E���@�F �@ �����̋���f���Ă��A�����ȏ�ɊC�̑������炵���B�@�@�@�R���u���^�ɐꍞ��ł���ӏ����Őܓ��B������3�����Ԃ��������R�������̍��Z�ɒʂ��ׂ��������]�Ԃœo�����ȂƊ��S�[���B��������2�q���炢�̋����Ȃ̂����A�Â�܂�̒����}�ȓo����ϑ��@�Ȃ��̃}�}�`�����œo��̂œr������͕����ĉ������Ƃ������A����������܂�30���ȏォ�������C������B �@�@�@�E�@�F �@ �ʂ������w�Z���甒�ǃ��l�͕����Ă�����Ƃ̋����B���w����̌㔼�A�F�l�Ƃ��ٓ̕V���ɗ��ĊC�߂Ȃ���A�܂��͍L���l���U�Ȃ��烍�}���E��������T�䏟��Y�ɂ��Č�荇�����̂��Ȃ������B



���ǃ��l1�@�@�@�k�A�`�̏o����]�� ���ǃ��l2�@�@�@���A�Őܓ���]�� ���ǃ��l3�@�@�@���A��O�ٓ̕V���H�Ɖ��̑Őܓ���]��
3��26���i�j����@�@�@�_���Ȃ������サ�B�_�̊��c���Ȃ����������[�͊����B�{���������͑����~��A�n�ʂ͔��������B
��C�����Ă���̂����m�Łu�[�ււ̉�A�v���@�@�i�����D�@�u���E�j�̋ɈӁv�j�@�F�@
�@�@ ����́u�J�j5000���C�̑�s�i�v�Ɍ�����悤�ɁA�����������܂�A�����A����ł����c�ׂ͒W�X�Ɩ����Ȃ��s���A�O�A�����Ȃ��Đ��X����������������B�������A��L�̖{��ǂ�ł��邤���A�l�ԂƂ��Đ��܂ꂽ����ɂ͂��̂悤�ȒP�����A���������Ő����A����ł����͓̂���Ǝv�킳�ꂽ�B�@�@�@�������́u�V�E�鍑��`�v�A�u�i�V���i���Y���v�A�u�@�������v�̎O���L�[���[�h�ɁA���オ��1�����O�ɍ������Ă���A�傫�ȑ�����푈�����E�I�ɋN����\��������B����A���ɐ��E�̂��������ł��ꂪ�n�܂��Ă���悤�ɂ��݂���ƌ����B�@�@�@�����j�~���Ă������߂ɂ͂ǂ�����������B�������͓�̉\�����w�E����B�u��͂�����x�[�ւɉ�A���邱�Ƃł��B�@�@�@�l���A�����̑����A���A�M���Ƃ�������C�̂����T�O�ɑ��āA�s�\���ƒm��Ȃ�����A����Ă����B����́A�o���g�̌����w�s�\�̉\���x�����߂Ă������Ƃł��B�@�@�@�ߑオ���E�ɋ߂����Ƃ͂������ł��B���̒���͂�����Ƃ���Ɍ���Ă���B�@�@�@�������A�ߑ����v�z�Ƃ��Ē�o���ꂽ���̂��A���Ƃ��Ƃ����s���Ă���̂������ł��B�@�@�@�[�֎�`�̋A���Ȃ��āA�����闝�O��T�O�𑊑Ή��������ʁA�l�X�͉����M���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��āA�����I�ɍs�����邾���ɂȂ��Ă��܂��B���܂�����o�ς��A�����s���w�҂̑z�肷��悤�Ȑ��E�ɂȂ��Ă��܂��B�@�@�@�����g�́A�ߑ�͌��E�ɋ߂Â��Ă�����̂́A����͂܂����炭��̂��Ƃ��ƍl���܂��B�i�����j�@�@�@���Ƃ���A�ߑ�̘g�g�݂̒��Ő푈���~�߂�ɂ͋ߑ�̗͂��g����������܂���B�@�@�@���ꂪ���̌����[�֎�`�ł��B���_���̂�T�C�N���ƌ����Ă�����������܂���B�v�@�@�@�u������̓v�����_���̐��_�A����������w�����Ȃ����E�x�ւ̃Z���X�����Ƃł��B�v�@�@�@�u���C���h���C�t�v�̓��������͖{�\�i�Ə����̊w�K�H�j�ɂ��������ĒW�X�Ɛ����A�킢�A�q�����c���Ȃǂ�����l�X�Ǝ���ł����B����Ȏp�ɂ͊������邵�A�w�Ԃׂ��ʂ����X����Ǝv���B����ǂ��A����������ƕ��G�Ő[���̂��l�Ԃ̑����Ȃ̂��Ȃƍl������ł��܂����B�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�C���Q���̎�d���B�T�c�}�C���̕������݁i�����Ɂj�B���l�M�̈ڐA�B�n�[�u���̐���
���@�F �@ �n�ʂ��Ă��邹�������̉ԁE�t�Ɉ�ԑ������₷���悤�ł��B �@�@�@���@�F �@ �`���[���b�v���ŋߍ炫�n�߂��t���[�W�A�����F����ԑ����̂͋��ʂ��Ă���A�z�̌�����荞�݂₷���F�Ȃ̂��ȂƊ����܂��B�������A�t���[�W�A�͉��F�̌�͔��A���A�Ԃ̏��Ȃ̂ŁA2�Ԏ�ȍ~�͏��s���̂悤�ł��B �@�@�@�E�@�F �@ ���Ƃ������A1�N�ȏ�O����C�ɂȂ�Ȃ���܂����ׂĂ��܂��A�t�̂��̎����A�V��̐Ԃ��炤���ɁA�����ĔZ���ɕω����Ă������܂��������B



���ɂ�����ꂽ�Ԏ�{ ���A�ԁA���̏��ɍ炢���`���[���b�v �J�G�f�H
�S�@�F �@ ������l�A��͐���C�͑������₩�ł��B



���㓇�ƒ���@1 ���㓇�ƒ���@2 ���㓇�ƒ���@3
3��27���i���j����̂��܂�@�@�@����3�������ő����~��Ă����B�v�X�̓܂�̓V�C�ŁA�����23.2���������ō��C�����{����18.0���~�܂�B
�u�F��@���̈ł̌������ɂ́@�P��������������v�@�i���ѐM�N�@�u�F��v�j�@�F�@
�@�@ 1�C2�T�ԕ��̐H���o���ɒ��̃X�[�p�[�Ɏ��]�Ԃōs������A���̋Ȃ�����Ă����B�@�@�@���̉̂����̂͐��N�Ԃ肩�A���␔�\�N�Ԃ肩�B�Ȃ������B�@�@�@��40�N�O�A19�̎��A4�N�Ԃ̋��D����������߂ď㋞���悤�Ǝv���������B�����Ŏd����������ɂ͉^�]�Ƌ������������������Ǝv���A���茧�k���̂n�s�ɏZ�ޗF�l�̃A�p�[�g��1�����قǔ��߂Ă��炢�i���ӁI�j�A�ׂ̂h�s�̎����Ԋw�Z�ɒʂ����B���̎��A�A�p�[�g�ŗF�l�����炩�ɉ̂��Ă��ꂽ�̂����̉̂��ƋL�����Ă���B�̎��A�Ȃ̑o���Ɋ������A�����Ɋo���Ĉꏏ�ɉ̂����i�ׂ̏Z�l�͂��邳���������Ƃ��낤�j�B�@�@�u�F��@�閾���O�̈ł̒��Ł@�F��@�킢�̉���R�₹�@�@�閾���͋߂��@�閾���͋߂��@�@�F��@���̈ł̌������ɂ́@�F��@�P��������������v�@�@�u�Ł@�@�閾���@�@�킢�@�@�P���������v�@�����̌��t���ׂĂ��g�ɐ��݂��B�@�@����ȔN������̂��낤���B1973�N�Ƃ������������������������̂��������̂��낤���B�@�@�@���́H�@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�g�E�����R�V�ƃG�_�}���̎�d���i�u���̔��v��3���A�u�Ƃ̑O�̔��v��1���j�B�g�}�g�A�i�X�A�L���E���A�s�[�}���̔��グ�B
���E���@�F �@ �̉Ԃ̃W�����O���Ő��Ԃ������Ă��Ȃ������̂��J���A�g�E�����R�V�A�G�_�}���̎�����݂ɔd���܂����B�肪�o�Ĉ���͍̉Ԃ�䰂����ɂȂ��ē������肪�悭�Ȃ��Ă���Ƃ��ꂵ���B����ɂ��Ă��A�c�}�~�͂���قǖ��ނ��Ƃ͏��߂Ēm��܂����B�������B �@�@�@�E�@�F �@ ���l�M�i�Αq��{�l�M�A����l�M�j�̃l�M�V��ł��B�Ԃ��炩���Ď���̂銔�ȊO�͓E���������Ƃ̂��ƁB�@�@�@���ׂĂĂ�Ղ�ɂ��ĐH�ׂ܂����B�����I



�g�E�����R�V�A�G���h�E�̐�1�@�@�@��d���O �g�E�����R�V�A�G���h�E�̐�2�@�@�@��d���� �l�M�V��
�S�@�F �@ ����̎ʐ^�B�ߑO�͔�����悤�ȋ����̂��ߌォ����ɂ��ė��đ��z�����ڂ낰�ɉ���ł��܂����B�k�������k���ɕς�����̂ʼn��������ł����̂ł��傤���B



�C�ƃ}���A��1�@�@�@�ߑO �C�ƃ}���A��2�@�@�@�[�� �C�ƃ}���A��3�@�@�@�[��
3��28���i�y�j����Ƃ��ǂ��܂�@�@�@�Œ�C���͍���܂ł�3���Ԃ�5����������Ă����̂��{����11.2���ƒg�����B�ō��C����28.2���ƂȂ�A�ē����Đ^�ē��ɋ߂��Ȃ�܂����B�@�@�@�Ƃ͂����A���͖k����A������A�삩��ƒ�߂Ȃ��A�ߑO�̎U�����͕��͖k���琁���Ă���̂ɉ_�͖k�ɓ����Ă���Ƃ����s�v�c�ȏɖڂ��ۂ����܂����B�����̕ω����������ƒn��Ə��ŕ��������Ⴄ�Ƃ������Ƃ�����̂��ȂƎv���܂����B
�@�F�@
�@�@ �@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�g�E�����R�V�ƃG�_�}���̎�d���i�u�Ƃ̑O�̔��v��1���j�B�g�E�����R�V�̎�d���i�Z���A3�j�B�g�}�g�i�z�[�������Y�j�̔��グ�B
���E���@�F �@ �z���˂��Ƃ݂ȉԂ��J���A���؈�ࣂ��̏�Ȃ��Ƃ�������ł��B�z���������蓖����Ȃ��ƊJ���Ȃ����A�A��Ƃ����Ƃ����Ԃɕ��Ă��܂��̂Ō����낪����B �@�@�@�E�@�F �@ �A�����ςȂ��̉䂪�Ƃɑ��āA�m�l�͖��N�������@��グ�A�엿����������ɂ܂��A���߂��Ƃ�����Ԃ�������̂Ŋ��̐������Ⴂ�܂��B���F�̊��������C������͉̂䂪�ƂƓ����ŁA�m�l�́u����[�A���F�͋��������v�ƌo�������������Ă���悤�ł����B



�m�l��̉�1�@�@�@���r���O�X�g���E�f�[�W�[ �m�l��̉�2�@�@�@���r���O�X�g���E�f�[�W�[ �m�l��̉�3�@�@�@�t���[�W�A
���E���@�F �@ ��u�Ԃ������Ă���悤���̑D�B�^�~�ɂ͍r�g�Ƌ����ɖ|�M����Ȃ���̍�ƂŌ��Ă�������q���q���ł������A�{���͉��₩�ȂȂ��̂�т肵������ł��B�u�����ƉE�I�@�X�g�b�v�I�v�Ȃǂ̐���������܂ł͂����蕷�����Ă��܂����B�務�ł�����ꂵ���B �@�@�@�E�@�F �@ �����̒I�͉�̂��A�~���Ă����|�͎�O�ɐς݁A�r�j�[���A�Ԃ�킹�Ă��܂��B��Ƃ��Ă�����Ɂu����ꂳ��ł��v�Ɛ����|����ƁA�u����[�A�N���đ���[��肽��������������āA�x���[�Ȃ��Ă������āA�|���ƕ����Ă���������v�Ƃ̂��Ƃł����B�@�@�@�T�c�}�C�������n�����̂��A�N���ɃJ���R���������̂Ɏg�������Ȃ̂ŗ��p����̂�1�C2�����̂݁B���̊��ɂ͐ݒu����̂���ςȘJ�͂Ǝ��Ԃ�H�����Ƃł��B�ق�Ƃ��ɂ���ꂳ��ł��B



�D�ƃI�m�g�b�� �D�ƃJ���R���I ��̂����J���R���I
3��29���i���j����@�@�@���������J���p���������A���̌�͐���B�@�@�@�u�ӂ邳�Ɩ��t�����v�̋L�O���̘e�ɂĒ��w�̓����ƉԌ���B�T�N���͂܂��ꕪ�炫�ł������A�z�𗁂т��ٓ����L���A���A���݂������Ԃł����B
56�C7�N�����Ă�����̂悤�Ɂi�c�t������̐搶�j�@�F�@
�@�@�@�Ԍ���̌�A�F�l�̗U���ŗc�t������̒S�C�̐搶���Z�܂�Ă���l�C���@��K�˂�B��������u�Ԃ���u����[�A�Ȃ������B�݂�Ȃ����q��������v�Ƃ��̍��̎v���o��N���Ɋo���Ă��Ă��ꂽ�̂ɂ͋������B�u�ق�Ƃɂ݂�Ȃ����q�������́B�`�N�͂��������Ƃ肵�ĂĂ����Ί�ŁA�a�N�͗����Ŋ����A�b�N�͉^���_�o���悭�Ď����̎v����O�ʂɏo���āA�c����͒N�ɂł��₳�����āE�E�E�v�Ɩ��O�������̓�����i�����Ĕɐ��̂��Ƃ�����Ă��ꂽ�B�@�@�@���ɑ��Ă��u���Ȃ��̂�������͂Ђ傤����ŁA���ꂳ��͗����������B�ǂ�Ȃ��q�����܂�邩�Ǝv���Ă����炱��ȂɌ��C�Ɂc�v�Ƃ���������Ă����������ӁB�@�@�@�搶�͎������̑�����قǂȂ����ē]���ꂽ�̂ŁA�������̂�54,5�N�Ԃ肾�낤�B�o���Ă��������Ă������ƂɊ��ӂ���ƂƂ��ɁA80�㔼���߂��Ă�����Ȃɂ������肳��Ă���̂Ɋ������A�����Ƃ����C�łƋF�������Ƃł����B�@�@�@ �@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�A�X�p���K�X�̈ڐA�B
�S�@�F �@ �tࣖ��ŁA��荇�����������A�z�C�������Ƃ�������ł����B



���w�����Ƃ̉Ԍ���1�@�@�@�җ�L�O���̍� ���w�����Ƃ̉Ԍ���2�@�@�@���A�����Ȃ� ���w�����Ƃ̉Ԍ���3�@�@�@�L�O���̑O�ɂ�
�S�@�F �@ �Ԕ��͂悭����ꂳ��Ă��āA�������̂悤�ł��B



�K�˂��C���@1 �K�˂��C���@2 �C���@���ꏏ�ɖK�˂��F�l�i�Ƃ̑O�̔��ɂāj
3��30���i���j����̂��܂�@�@�@�܂�ƌ����Ă����̂��ǂ����B�C�ۂ̂����������̂������A�ߌ�͗z�͌����Ă���̂ɂ��ڂ낰�Ō��z�I�ȕ��i�ł����B���͂قƂ�ǂȂ��ŁA���̂悤�ȊC�ł��B
�w�Z���x�Z�ƂȂ�A�S���k�����_�ɍs�����I�H�i1965�N�A���w1�N���̎��j�@�F�@
�@�@�@����A���w�̓����Ƃ̉Ԍ���̂Ƃ��A�u1�N���̉āA�ߌ�A�w�Z���x�݂ɂȂ��Đ��k�S�����_�ƂɎ�`���ɍs������ˁv�Ƃ̔���������A���̌サ�炭���̘b�Ő���オ�����B�@�@�@���̔N�͋�O�̋�~�J�Ŋ��ƂȂ�A�A�����T�c�}�C���̕c�������̂قƂ�ǂ̔_�ƂŌ͂�Ă��܂����B�����̓T�c�}�C���i�J���R���j�͒��̊�Y�Ƃ������̂ŁA���̌o�ς����ׂ��Ƃ������Ƃ��낤���A���w���S����_�Ƃɑ��肾���ĐV���Ȉ��d����A�����Ƃ���`�킹���Ƃ̂��ƁB�@�@�@���̃c���ȂǐG�������Ƃ̂Ȃ����̎q�����͂قƂ�ǐ�͂ɂȂ�Ȃ��������A��͂��`�����Ƃ���l�����ɂ���ƋC��������悤���B�S���̓������́u�������i�������j�������ȁ[�A������i������j�l�Ċ��ŁA�o���o������������A�͂��ǂ�����B����ρA���Ă���Ă悩����������Ȃ��납���v�Ƃ̊��z�������B�@�@�@���͂܂������o���Ă��Ȃ��B���Ԃ�A���̐����A������w�Z���x�܂���Ĕ_��Ƃ����Ă����̂ŁA�w�Z���ߌ�ɋx�Z�ɂȂ������ƂȂǒm������Ȃ������̂��ȂƎv���B�@�@�@���̎��ゾ������A�ꕔ�̐��k�̐e�i�_�Ɓj�̂��߂Ɋw�Z���x�Z�ɂ��A���������k�S����_�Ƃ̎�`���ɔh������ȂǍl�����Ȃ����낤�B����Ȃ��Ƃ�������A�����̐e�̃N���[���Ŋw�Z����Ⴢ���̂ł͂Ȃ����B�@�@�@�n�����������Â��ǂ���������ȁA�Ƃ����C���������Ƃł����B�@�@�@ �@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�A�X�p���K�X�̈ڐA�i�����j�B�u�O�̔��v�̑����B�u���̔��v�̉Ԓd�̑����B
���@�F �@ 2�N�O�A�ю������ݍ������悤�ȕR��Ŏ�̂Ђ�ɏ�邭�炢�̍���A�����̂��A���͂���Ȃɍ���A���a1m�قǂ̌����@���Ă���Ǝ��o���܂����B�@�@�@�����������鐨�������悤�Ǝ�肪�o�Ă��H�ׂ��ɗ��܂������A�ڐA�������߂���1�N�͉䖝���K�v��������܂���B �@�@�@���@�F �@ �E�����������̂ŁA�o�ׂ���ߒ��Ńn�l�����́B���̂킪�Ƃ̂Ɣ�ׂ�ƈႢ����R�ł��B�@�@�@�����L�Y���������������A���O���E�l�Y�~�����������Ղ����邯��ǁA�V�W���K�̔��������ɕς��͂Ȃ��B�@�@�@ �@�@�@���@�F �@ ���̉Ԃ̖��O���W���[�}���A�C���X���Ƃ́A���m���ݏZ�̓������ɋ����Ă��炢�܂����B�䂪�Ƃɂ͔Z�����̊������������ɍ炫����Ă���܂����A�����܂����炵���B



�ڐA�����A�X�p���K�X �m�l�ɒ������V�W���K �m�l��̃W���[�}���A�C���X
�S�@�F �@ ��1�T�ԑO�A24���̎ʐ^�ł��B�{���̃{���[�b�Ƃ����i�F���炷��Ƃ���Ȃ������肵����C�̓�������ƍĊm�F�ł��B



���ꂽ�C1�@�@�@����]�� ���ꂽ�C2�@�@�@����]�� ���ꂽ�C3�@�@�@���]��
3��31���i�j�܂莞�X�J�@�@�@�ߑO�̑�����������J�Ƃ̗\�����̂ŁA�ߌ�͏����d�������邵���Ȃ��Ǝv���A�������X�s�[�h���グ�ĉJ�O�ɂ��ׂ��d���Ɋ��𗬂��B���A�ߌ�ɂȂ��Ă����J�Œn�ʂ͂قƂ�ǔG�ꂸ�B���Ǘ[���܂œ����Â��߂̈���ł����B��������ǁB
����ɂǂ̂��炢�R�����e��邩�@�i�f��@�u�����e�E�E�H���V���v�j�@�F�@
�@�@�@�����ю��ABS�ł��̉f�����f���Ă����B�@�@�@�s�i�C�̂��߁A�܂��q��o�c�ɑ厑�{�����o���Ă��č�ň͂��Ă̎���ƂȂ��Ă������߁A�J�E�{�[�C�E�q������ʂɉ��ق�������Ă�������̕���B�J�E�{�[�C�̎d���̖��l�ƕ]���̍����E�H���V�������A���Ԃ͂ǂ�ǂ���ق���A���N�̃p�[�g�i�[���G�݉��̏����ƌ������ĊX�̐l�ƂȂ��Ă����B�u�q������߂�̂��H�@�@�X�ɏZ�߂�̂��H�@�v�Ƃ̖₤�E�H���V���ɁA�u�����������B�@�J�E�{�[�C�͏�����v�ƃp�[�g�i�[��������V�[���͂��̔߂��������B�@�������畨��͑�c�~�Ɍ������̂����A����͊�������B�@�@�@����ɂ��Ă��A�J�E�{�[�C�̏I���̎���łȂ�������o�ꂷ��j�����̔ߌ��͂Ȃ�������������Ȃ��Ǝv���ƁA�f��̒��̘b�Ȃ���l��������ꂽ�B�~�߂悤�̂Ȃ�����̑傫�ȗ���ɂǂ��܂ōR�����A�ǂꂾ���e��邩�B����͍������̎�����e���̋i�ق̉ۑ�Ȃ̂��Ǝv�킳�ꂽ�B�@�@�@ �@�@�@�@�@
�{���̍�Ɓ@�F�@ �@�@�u�Ƃ̑O�̔��v�ɓ�\���_�C�R���̎�d���B�@�@�J�{�`���E�������Ȃǂ̐A�����Â���i�u�Ƃ̑O�̔��v1���A�u���̔��v3���A�u���̔��v4���j
���E���@�F �@ ���͍���A���͖{���̎ʐ^�ł��B�R���n�̔����Ԃł����A2�C3�֍炫�n�߂��ȂƎv���Ă����琔���ԂŖ��J�ɂȂ�܂����B��y�F�̗t�������ɉ萁���Ă��������ł��B �@�@�@�E�@�F �@ ��N7���Ɏ��d�����j���W�����̉Ԃɖ�����Ă܂����݂ł��B�`�̓S�c�S�c���Z�N�V�[�ł����A�~�̊����ɑς������������͊Â��ăW���[�V�[�ŁA�܂��ϕ��ɓV�Ղ�ɂƐH�ׂĂ��܂��B�@�@�@



�킪�Ƃ̍������J1 �킪�Ƃ̍������J2 �{�����n�̃j���W���i�X�������́j
�S�@�F �@ ����̎ʐ^�ł��B��́u�g�̂Ȃ̎����Ȃ��ˁv�Ƃ̌��t�ǂ���A���Ԃ��~�܂����悤�Ȕg�Ȃ��A���Ȃ��̊C�ł����B



�g�̂Ȃ��C1 �g�̂Ȃ��C2 �g�̂Ȃ��C3
���g�b�v�ɖ߂�